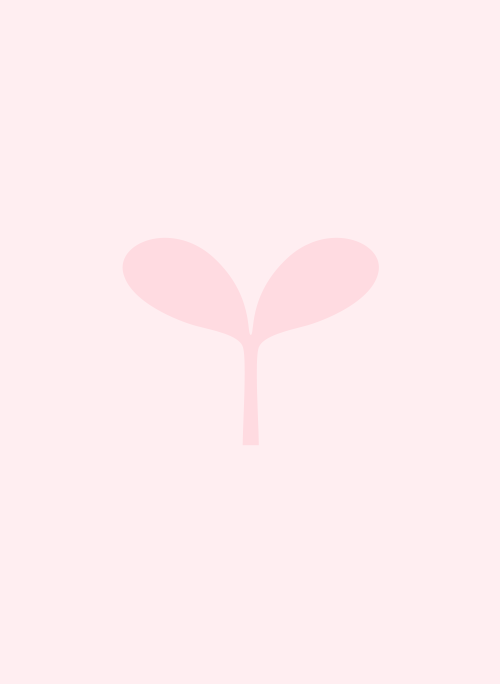いつもならきちんとお母さんに教わったとおり、誰もいなくったって「おやすみなさい」と挨拶をして寝るのですが、この日のネモはだんまりでした。
もそもそと布団の中に潜り込むと、頭から毛布を被ってあぐらをかきました。
「ふん。どうせお母さんは来ないもの。僕が悪い子になっても平気さ」
パチン、と落花生の殻をむきながら呟きます。
バリバリと薄皮をはがして頬張り、ネモは満足げに頷きました。
楽しいはずでした。
いけないことを思いっきりして、大好きな落花生で口の中はいっぱい。
このまま明日を迎えても、ネモを叱る人は誰もいないのです。
ところが、ネモの心はどんどん穴のあいた風船のようにしぼんでいきました。
美味しいはずの落花生は、なんだか味気なくてパサついていました。
肩を落とし、背中を丸めたネモの目に、うっすら涙が溢れてきました。
「お母さんの、嘘つき」
か細い声で呟いた、そのときでした。
もそもそと布団の中に潜り込むと、頭から毛布を被ってあぐらをかきました。
「ふん。どうせお母さんは来ないもの。僕が悪い子になっても平気さ」
パチン、と落花生の殻をむきながら呟きます。
バリバリと薄皮をはがして頬張り、ネモは満足げに頷きました。
楽しいはずでした。
いけないことを思いっきりして、大好きな落花生で口の中はいっぱい。
このまま明日を迎えても、ネモを叱る人は誰もいないのです。
ところが、ネモの心はどんどん穴のあいた風船のようにしぼんでいきました。
美味しいはずの落花生は、なんだか味気なくてパサついていました。
肩を落とし、背中を丸めたネモの目に、うっすら涙が溢れてきました。
「お母さんの、嘘つき」
か細い声で呟いた、そのときでした。