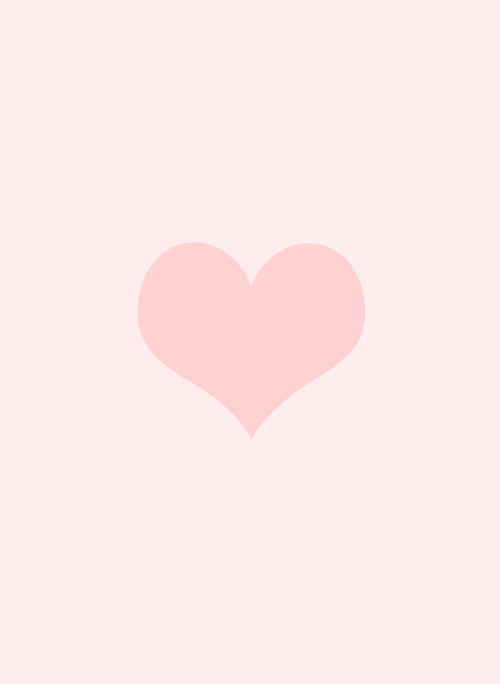「ひょっとしたら、将人センパイはあたしを嫌っているのかもしれない」
部員のみんなはロードワークに出ていた。早智子さんも自転車で同行している。
洗濯を終えたあたしは千晴センパイと一緒に、お茶の準備をしていた。
1時間半の練習のあと、次の対戦相手のビデオを観ることになっていた。
給湯室から冷えた麦茶入りのやかんを運びながら、あたしは今朝の一件をゆっくりと話した。
千晴センパイは、ときどき質問をはさみながら、聞いてくれた。
「顔も見たくない。おまえみたいなミーハー女、とっとと辞めちまえ! ……って、今頃思っているかも……」
あはは、と千晴センパイは笑いとばす。
「将人くんの大っ嫌いなロードワークの最中だよ。それどころじゃないでしょ」
「そうかなあ」
「そうだよ」
「……早智子さんも、楽観的なこと言って、あたしの後押しをしたんだよね。なのに結果がコレだもの」
「そんなに何もかも疑わなくたって……。気持ちはわかるけどね」
溜め息をつくあたし。
なんでこう、うまくいかないのかな。あたしは将人センパイから愛してもらえたら、ほかのことなんてどうでもいいのに。
部室の時計の下――鏡に映るあたしは、そうするつもりはなくても、上目づかいでこちらを見ている。
ホットビューラーでカールをつけたまつ毛が、くりっとした目を縁どっている。そばかすこそないけど、日焼けした顔。
ルビーブラウンの髪はそのままだと風と埃でぐしゃぐしゃになるから、部活のときだけふたつわけの編みこみ。サッカー部の揃いのダークグレーのジャージだって似合ってる。
……なのに唇は、小さくすぼまって不満の形になっている。
部員のみんなはロードワークに出ていた。早智子さんも自転車で同行している。
洗濯を終えたあたしは千晴センパイと一緒に、お茶の準備をしていた。
1時間半の練習のあと、次の対戦相手のビデオを観ることになっていた。
給湯室から冷えた麦茶入りのやかんを運びながら、あたしは今朝の一件をゆっくりと話した。
千晴センパイは、ときどき質問をはさみながら、聞いてくれた。
「顔も見たくない。おまえみたいなミーハー女、とっとと辞めちまえ! ……って、今頃思っているかも……」
あはは、と千晴センパイは笑いとばす。
「将人くんの大っ嫌いなロードワークの最中だよ。それどころじゃないでしょ」
「そうかなあ」
「そうだよ」
「……早智子さんも、楽観的なこと言って、あたしの後押しをしたんだよね。なのに結果がコレだもの」
「そんなに何もかも疑わなくたって……。気持ちはわかるけどね」
溜め息をつくあたし。
なんでこう、うまくいかないのかな。あたしは将人センパイから愛してもらえたら、ほかのことなんてどうでもいいのに。
部室の時計の下――鏡に映るあたしは、そうするつもりはなくても、上目づかいでこちらを見ている。
ホットビューラーでカールをつけたまつ毛が、くりっとした目を縁どっている。そばかすこそないけど、日焼けした顔。
ルビーブラウンの髪はそのままだと風と埃でぐしゃぐしゃになるから、部活のときだけふたつわけの編みこみ。サッカー部の揃いのダークグレーのジャージだって似合ってる。
……なのに唇は、小さくすぼまって不満の形になっている。