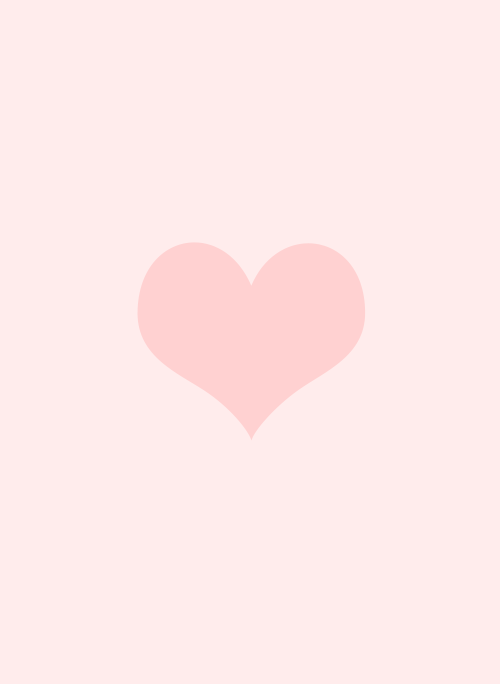月曜日から、川崎くんの努力の日々がはじまった。
「かしわー。問四の2って、ヨウ素液?」
「ベネジクト液よ」
「3は酵素か」
「……うん。そうね」
朝学習から六時間目まで、ずっとこの調子。わからないところを矢継ぎ早に聞いてくる。
私だって先生じゃないし、塾にも行っていないから、答えられないものもあるわけで、そうなると次の日までに調べておく必要がある。
『そんなの、先生に聞きなさいよ』って、言えばいいのかもしれない。
それに、30位以内という条件はさすがに厳しかったかな……と、ほんの少し、同情していたりもする。
151番以上、順位をあげるなんて、限りなく不可能に近い。
私だったら、そんなかけには乗らない。できっこないもの。がんばる彼を見るうちに、申しわけなくなってきた。
――私もできるだけ、協力しよう。
「いったい、どうしちゃったの? ジュン」
「ガリガリと音がしそうなくらい、勉強してるけど……」
「潤くん、中間がそんなに悪かったの?」
コレキヨ君や、通りすがりの女の子たちが、そばにいる私に尋ねてくる。ささやくような声で。
けれども、川崎くんにもしっかりとそれは聞こえていて、そのつど、
「実は期末テストで、30位以内を狙ってるんだ」
とだけ、言った。
「へえ」
「すごいね」
「ほめるのは、あとにしてね」
川崎くんは愛想よく微笑む。クスクス笑いながら、女の子たちは立ち去る。
ほんと、女の子の扱いがうまいなあ。
「どうせなら、立候補のこともそれとなく話してみたら? 力になってくれるんじゃない?」
川崎くんのサラサラと数式を書きあげるさまを眺めつつ、私が言うと、その細身のシャープペンシルが止まった。
私たちはしばし、見つめあった。
怒っているようにも見える彼の瞳から、視線を動かせない……。
川崎くんの声がした。
「……さっちゃん」
脱力。
ひざの上から教科書が滑り落ちた。拾いあげながら、私は、
「あーのーねーっ!」
「かしわー。問四の2って、ヨウ素液?」
「ベネジクト液よ」
「3は酵素か」
「……うん。そうね」
朝学習から六時間目まで、ずっとこの調子。わからないところを矢継ぎ早に聞いてくる。
私だって先生じゃないし、塾にも行っていないから、答えられないものもあるわけで、そうなると次の日までに調べておく必要がある。
『そんなの、先生に聞きなさいよ』って、言えばいいのかもしれない。
それに、30位以内という条件はさすがに厳しかったかな……と、ほんの少し、同情していたりもする。
151番以上、順位をあげるなんて、限りなく不可能に近い。
私だったら、そんなかけには乗らない。できっこないもの。がんばる彼を見るうちに、申しわけなくなってきた。
――私もできるだけ、協力しよう。
「いったい、どうしちゃったの? ジュン」
「ガリガリと音がしそうなくらい、勉強してるけど……」
「潤くん、中間がそんなに悪かったの?」
コレキヨ君や、通りすがりの女の子たちが、そばにいる私に尋ねてくる。ささやくような声で。
けれども、川崎くんにもしっかりとそれは聞こえていて、そのつど、
「実は期末テストで、30位以内を狙ってるんだ」
とだけ、言った。
「へえ」
「すごいね」
「ほめるのは、あとにしてね」
川崎くんは愛想よく微笑む。クスクス笑いながら、女の子たちは立ち去る。
ほんと、女の子の扱いがうまいなあ。
「どうせなら、立候補のこともそれとなく話してみたら? 力になってくれるんじゃない?」
川崎くんのサラサラと数式を書きあげるさまを眺めつつ、私が言うと、その細身のシャープペンシルが止まった。
私たちはしばし、見つめあった。
怒っているようにも見える彼の瞳から、視線を動かせない……。
川崎くんの声がした。
「……さっちゃん」
脱力。
ひざの上から教科書が滑り落ちた。拾いあげながら、私は、
「あーのーねーっ!」