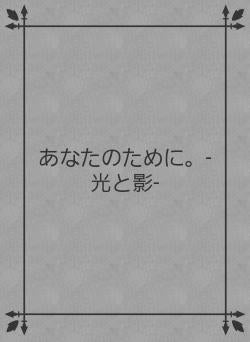美味しそうにシュークリームを食べる深侑を見ると、深侑の口の端にカスタードがついていた。
「深侑。クリームついてる」
「……ん、」
深侑は食べるのをやめて私の方に体を寄せた。
私はカバンからティッシュを出して口の端についたカスタードを取ってあげる。
ティッシュを丸めてテーブルに置いて再びお弁当を食べ始めると、向かいから二つの視線を感じて箸を止める。
葵ちゃんは眉間にシワを寄せて何度も頷いていて、柊花はラーメンを食べる手前で口を開けたまま止まっていた。
「…え、な、なに……?」
「あ、いや、これが"深侑ママ"かと思いまして」
「え?深侑ママ?何それ」
葵ちゃんの言ってることが理解できない。
「女子の間で噂になってるんですよ。
深侑の隣には深侑に世話を焼く美人のセンパイがいるって。
完璧に夏生センパイのことだろうと思ってたんですけど、それを目の当たりにすると確かにと思いまして」
「いやいやいや!確かにじゃないでしょ……!」
こうやって深侑に世話を焼いてるところを見られて、更には噂にまでなってるなんて……!
こんな公衆の面前でやってればそうなるか。
当たり前にやってたから気づかなかった。