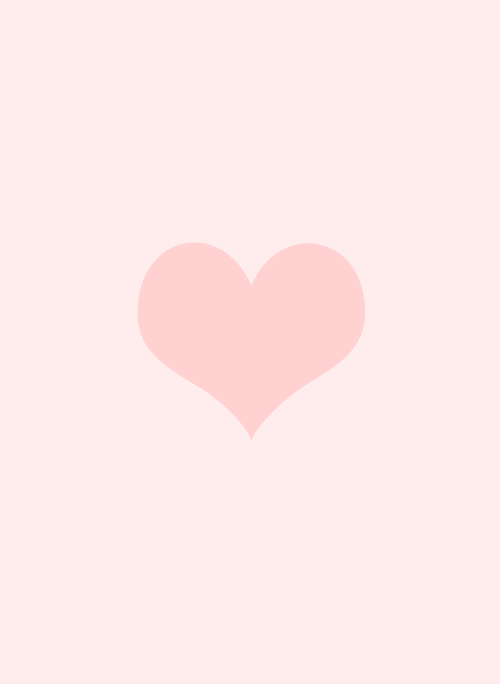温度の消えた手首に、冷たい空気が当たる。
背後にあった気配が、スッと動いて私の横を通りすぎた。
目に映った予想通りの彼の後ろ姿。
さっきまでゼロに近かった距離が、二歩、三歩、と離れていく。
行ってしまう。
「待って」
思わず身を乗り出して叫ぶと、彼がピタリと足を止めた。
はっと息を呑む。
自分で待てと呼び止めておきながら、緊張が体を駆け抜ける。
立ち止まった彼がゆっくり振り返って、いつもと同じ優しい色を含んだ切れ長の瞳と、視線が繋がった。
「あ、」
漏れ出た声に反応するように、彼の表情が緩んだ気がして、トン、と胸の奥が音を鳴らす。
「こわがらせて悪かった」
低く落ち着いた、静かな声。
そのわずかな空気の振動が鼓膜を震わせた瞬間、心臓がぎゅうっと締め付けられた。
どうして。
なんで。
叫びたいのに、声にならない息だけが喉をすり抜けていく。
「早く戻ろう」
黒い服の女性の声で、彼の視線が外れた。
「ああ」
短く答えて彼女に視線を移した彼の後ろ姿が、また遠くなっていく。
待って。
叫ぶ声は音にならないまま、彼の遠くなる後ろ姿を見送る。
一歩、踏み出した足の小指が、硬い何かに当たった。
「いっ、」
痛みに身を屈めて、ぶつかった小指を摩る。
どうやら床に置かれた木箱の角で打ったらしい。
じんじんと尾を引く痛みに耐えながら、もう一度彼らのいた場所に視線を上げると。
目に映ったのは、誰もいない研究部屋。
慌てて見回してみても、もう、二人の姿はどこにもなかった。
背後にあった気配が、スッと動いて私の横を通りすぎた。
目に映った予想通りの彼の後ろ姿。
さっきまでゼロに近かった距離が、二歩、三歩、と離れていく。
行ってしまう。
「待って」
思わず身を乗り出して叫ぶと、彼がピタリと足を止めた。
はっと息を呑む。
自分で待てと呼び止めておきながら、緊張が体を駆け抜ける。
立ち止まった彼がゆっくり振り返って、いつもと同じ優しい色を含んだ切れ長の瞳と、視線が繋がった。
「あ、」
漏れ出た声に反応するように、彼の表情が緩んだ気がして、トン、と胸の奥が音を鳴らす。
「こわがらせて悪かった」
低く落ち着いた、静かな声。
そのわずかな空気の振動が鼓膜を震わせた瞬間、心臓がぎゅうっと締め付けられた。
どうして。
なんで。
叫びたいのに、声にならない息だけが喉をすり抜けていく。
「早く戻ろう」
黒い服の女性の声で、彼の視線が外れた。
「ああ」
短く答えて彼女に視線を移した彼の後ろ姿が、また遠くなっていく。
待って。
叫ぶ声は音にならないまま、彼の遠くなる後ろ姿を見送る。
一歩、踏み出した足の小指が、硬い何かに当たった。
「いっ、」
痛みに身を屈めて、ぶつかった小指を摩る。
どうやら床に置かれた木箱の角で打ったらしい。
じんじんと尾を引く痛みに耐えながら、もう一度彼らのいた場所に視線を上げると。
目に映ったのは、誰もいない研究部屋。
慌てて見回してみても、もう、二人の姿はどこにもなかった。