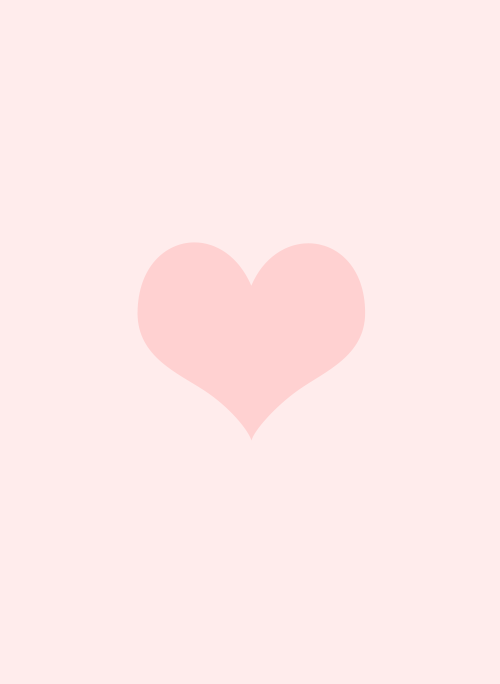「いえ、そうではなくて今日、少し元気がないような」
どこが違うと言われてもハッキリは答えられないけれど、なんかいつもと違う気がする。
「本当、お前だけはそういうの気づくんだな」
「えっ」
いつも会社ではみんなの期待する一ノ瀬さんを作ってる彼。負担はないと言っていたけれど、作っている自分がいるってことは、少なからず自分の気持ちを犠牲にしてるということだ。
「ほら早く行けよ。待ち合わせ遅れるぞ」
しかし、私を追い払うように手をシッシッと振る。少し心配だったけれど、時間も迫ってきていたので、ここで帰ることにした。
私はカバンを引き寄せドアの前に向かう。
「疲れてるならいつでも呼んで下さい。私でよければ力になりますから」
なんでそんなこと言ったのか自分でも分からない。でも気づけばそんなことを伝えていた。
会議室のドアを捻り出ようとした時、つぶやくように彼が言う。
「お前って、たまには可愛いこと言うのな」
しみじみと、でも口角を上げて意地悪に。
「たまにってなんですか!もう!」
やっぱり心配して損した!