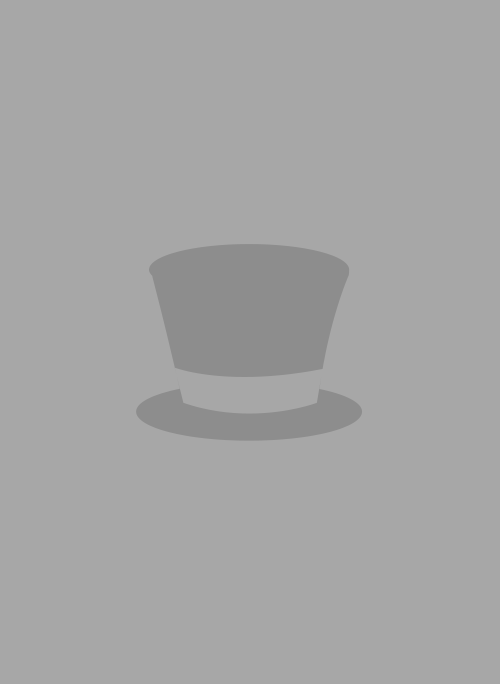オフィス街のビルにはいくらか明かりが点っているが、既に日付は変わってしまっている。
深夜の静けさというのは、無いらしい。
「賑やかなのは嫌いじゃないが、耳障りな音も聞こえてくるな」
屋上から地上を見下ろす男が呟くと、白い吐息は冬の寒空へと溶けていた。
「だから、別の場所にしようと私は何度も申したはずですよ、旦那!まったく、理想の田舎暮らし、静かな地でのんびり過ごす私の楽しみをどうしてくれるんです!?」
黄昏る男の空気を壊す声が響くと、男の肩に休めるようにして止まったのは一匹のコウモリだ。
良くできた玩具の様にコウモリは男の肩で、説教節を止めることはない。
「都会の人間なんてね、絶対に私達の事なんて理解するどころか、鼻で笑うか白い目で見るのがオチですよ。さあさあ、今からでも遅くないですから、考え直しましょう、旦那!」
「リルム、それは偏見だぞ。都会の方が、色んな人間は居るものだ。大体、田舎のような閉鎖的な空間にいる女より、こういう場所で育った女の方が、良い匂いがしそうだろう」
「旦那の方こそ偏見どころか、一歩間違えれば変質者発言です……ぐふっ」
肩に乗ったリルムと呼ばれたコウモリは、男の手によって押し潰されて、カエルのような音で鳴いてしまっている。
「とにかく、俺はここに決めた。俺の決定は絶対だ……ここで、俺の事を求めてくる奴に救いの手を差し伸べてやろうじゃないか」
リルムの意見などまるで選択肢に無いと一蹴した男は、怪しげに微笑んで、その姿を消した。