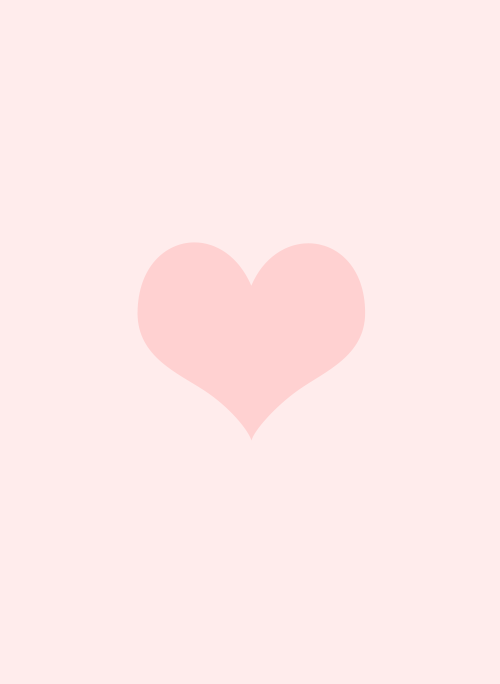「リンダちゃんこっち座って。」
いつの間にかカオリさんが、カウンターに居た彼女を引っ張ってきていて、一番隅っこに座っている。
私から一番遠い場所だった。
レンと久しぶりだねって声をかけたりしてるけど、エイジ君とは目を合わせようともしなくて、やっぱり気まずいんだろうなって思う。
エイジ君はそんな彼女のことを、悲しげな表情でずっと見ているのがわかった。
エイジ君の手が汗ばんでいる、緊張してるんだな。
「話があるんでしょ、ちゃんと話していいよ。」
カオリさんはそんな風に言うけれど、きっとこの状況じゃ無理だよね。
繋いでいた手を離すと、私は彼の手の甲を二回叩いて、行っておいでと合図する。
ここじゃ話しずらいだろうに・・・
サマソニのあのホテルの時だって、エイジ君は私とビトが2人で話しているのを黙って見守ってくれたんだもの、わたしも大丈夫。
やっぱり無理だとエイジ君は呟いて、いきなり立ち上がると、リンダさんの手を取って2人で店を出て行った。
最後に振り返って、
「モモ、俺ちゃんとけりをつけてくるから、待ってろ。」
そんな風に言ってくれるから、私はただ頷いて堪えるしかなかった。
「いいの二人にして?」
レンが不安そうに言うけど、しょうがないじゃんって私は俯いた。
若いバイト風の店員さんが、ウーロン茶とビールを持ってきてくれて、先に飲んで待ってようってカオリさんに言われて、私たちは三人で料理のメニューを選んだ。
「何で出てくかね?せめて向こうで話すとかすればいいのに。」
レンがさっきのバイトの人にガンガン注文をしてからぼやいた。
「そりゃ、私が居たら話せないでしょ、やっぱり。」
私はリンダさんのことよく知らないもの・・・
「だってさ、この前ホテルでビトと話してたときも平気だったじゃん。なんかあったらどうすんだよ。」
何故か私より、レンが怒っているのがおかしかった。
「そうなったらそうなった時だよ、あっちの絆の方が深かったってことでしょう?」
私は何気に覚悟していた。
だって好きになったときからわかっていたもの、エイジ君の心の中には、ずっとあの人が居るってことを。
「エイジ君はもうビトと仲いいじゃん、普通に友達じゃない。だから私とリンダさんとは違うんだよ。」
注文したメニューは、次から次へと机に並べられて、レンはやけくそのようになって食べている。
私も少し手を伸ばすと、どれも美味しくてもしかしてこういう味でエイジ君は育ってきたのかなって思った。
いつも元気なカオリさんが、何故かずっと無口だ。
「カオリさんも、食べましょうよ。」
そう声をかけたけど、まだ大丈夫って言いながら箸を付けようとはしなかった。
そういえば、ビールもまだ半分以上残ってるな、今日は飲まないのかな?いつもは一気に一杯空けちゃうのに。
「モモちゃんはエイジ君信じてるでしょ?戻ってくるって。」
そんな風に聞かれたけど、信じてるって言えば信じてるのかな? どちらを選んだとしてもエイジ君の決めることだもの。
「正直わからないです。だって私は彼女のこと知らないから・・・」
レンはどう思ってるんだろう・・・そうやって聞いてみると、いいずらそうにしている。
またきっと、何か言っちゃいけないことを知ってるんだろうなって思った。
「僕も正直わかんない、だって2人とも知らないでしょ、エイジとリンダさんがどんな感じだったか。僕は知ってるから・・・」
いつの間にかカオリさんが、カウンターに居た彼女を引っ張ってきていて、一番隅っこに座っている。
私から一番遠い場所だった。
レンと久しぶりだねって声をかけたりしてるけど、エイジ君とは目を合わせようともしなくて、やっぱり気まずいんだろうなって思う。
エイジ君はそんな彼女のことを、悲しげな表情でずっと見ているのがわかった。
エイジ君の手が汗ばんでいる、緊張してるんだな。
「話があるんでしょ、ちゃんと話していいよ。」
カオリさんはそんな風に言うけれど、きっとこの状況じゃ無理だよね。
繋いでいた手を離すと、私は彼の手の甲を二回叩いて、行っておいでと合図する。
ここじゃ話しずらいだろうに・・・
サマソニのあのホテルの時だって、エイジ君は私とビトが2人で話しているのを黙って見守ってくれたんだもの、わたしも大丈夫。
やっぱり無理だとエイジ君は呟いて、いきなり立ち上がると、リンダさんの手を取って2人で店を出て行った。
最後に振り返って、
「モモ、俺ちゃんとけりをつけてくるから、待ってろ。」
そんな風に言ってくれるから、私はただ頷いて堪えるしかなかった。
「いいの二人にして?」
レンが不安そうに言うけど、しょうがないじゃんって私は俯いた。
若いバイト風の店員さんが、ウーロン茶とビールを持ってきてくれて、先に飲んで待ってようってカオリさんに言われて、私たちは三人で料理のメニューを選んだ。
「何で出てくかね?せめて向こうで話すとかすればいいのに。」
レンがさっきのバイトの人にガンガン注文をしてからぼやいた。
「そりゃ、私が居たら話せないでしょ、やっぱり。」
私はリンダさんのことよく知らないもの・・・
「だってさ、この前ホテルでビトと話してたときも平気だったじゃん。なんかあったらどうすんだよ。」
何故か私より、レンが怒っているのがおかしかった。
「そうなったらそうなった時だよ、あっちの絆の方が深かったってことでしょう?」
私は何気に覚悟していた。
だって好きになったときからわかっていたもの、エイジ君の心の中には、ずっとあの人が居るってことを。
「エイジ君はもうビトと仲いいじゃん、普通に友達じゃない。だから私とリンダさんとは違うんだよ。」
注文したメニューは、次から次へと机に並べられて、レンはやけくそのようになって食べている。
私も少し手を伸ばすと、どれも美味しくてもしかしてこういう味でエイジ君は育ってきたのかなって思った。
いつも元気なカオリさんが、何故かずっと無口だ。
「カオリさんも、食べましょうよ。」
そう声をかけたけど、まだ大丈夫って言いながら箸を付けようとはしなかった。
そういえば、ビールもまだ半分以上残ってるな、今日は飲まないのかな?いつもは一気に一杯空けちゃうのに。
「モモちゃんはエイジ君信じてるでしょ?戻ってくるって。」
そんな風に聞かれたけど、信じてるって言えば信じてるのかな? どちらを選んだとしてもエイジ君の決めることだもの。
「正直わからないです。だって私は彼女のこと知らないから・・・」
レンはどう思ってるんだろう・・・そうやって聞いてみると、いいずらそうにしている。
またきっと、何か言っちゃいけないことを知ってるんだろうなって思った。
「僕も正直わかんない、だって2人とも知らないでしょ、エイジとリンダさんがどんな感じだったか。僕は知ってるから・・・」