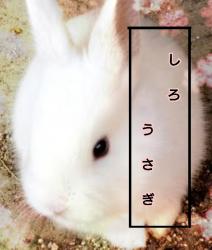まぁ私は絶対彼氏にしたいなんて思わないけど。
12月の冷たい風が吹きさらす屋上に好んで足を運ぶのはどうやら私だけのようで。
それはそれは喜ばしいことでもあったのに。
太雅に見つかってからと言うもの、お昼休みにここに来る私の後をストーカーの如く追ってくる。
「別にこんなとこわざわざ来なくても教室に構ってくれる女の子いっぱいいるでしょ」
「んー、まぁそうだけど。
今はここでいいや。
それより那菜こそ女の子の集まりに参加しなくていーわけ?」
「いいの。
独り行動の時間も無いとしんどいし」
特に学校で孤立してる訳でもない。
そこそこ仲の良い友人にも恵まれている。
異性の友人もちらほらいる。
けれど彼氏は……
当分いらない。
彼らは無理矢理な理由をつけては平気で離れていく。
そんな人達ばかり。
「ふーん」
「なに聞いといて興味無いわけ」
「お、構ってほしいのかー?」
「誰がこの会話聞いてそんな解釈するの」
だから誰だって程よい距離感で。
有難いことに友人は皆良い人達ばかりで。
余計に異性の友人が恋人に変わってしまうのが嫌だった。
そうなってしまった途端、彼らも信用出来なくなってしまいそうで……。
「那菜は人付き合いが悪い訳じゃないけど何となくさ。
放っておけない陰みたいなのがあるんだよなー」
「……なぁ、」
「だからなんか構いたくなるのかもな、うんうん」
女ったらしのくせして妙に鋭い。
どさくさに紛れて抱き付いてきそうになった太雅を遠慮無しに蹴っ飛ばす。
きっと沢山の女の子と接してきたから繊細な女の子の気持ちというのはよく分かるのかも知れない。
こっちからしたら、それ以上踏み込まないで欲しいものだけど。
正直、太雅ともこうして憎まれ口を叩くような関係で充分だ。