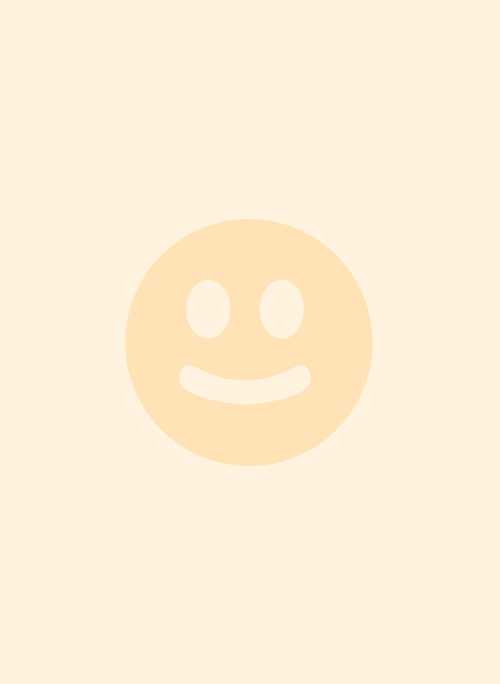「教師としての自分に自信が持てないのならば」
鈴木さんの被っている段ボール箱。
その内側で、微笑む気配があった。
「仲間として力になってあげるといいのです。歳上のお姉さんとして力になってあげるといいのです。友人として、力になってあげるといいのです」
「仲間…」
「貴女は、龍一郎一味の仲間なのでしょう?」
「……」
すずの不安の表情は和らぎ、微笑みが戻ってくる。
「分かったの、パパ。忠告有り難うなの」
「I don't come to fee.(礼には及びません)」
得意のネイティブイングリッシュで告げる鈴木さん。
「では忠告ついでにもうひとつ」
鈴木さんは、すずの胸元を指差す。
同時に、ハラリと落ちるすずのバスタオル。
鈴木さんの被っている段ボール箱。
その内側で、微笑む気配があった。
「仲間として力になってあげるといいのです。歳上のお姉さんとして力になってあげるといいのです。友人として、力になってあげるといいのです」
「仲間…」
「貴女は、龍一郎一味の仲間なのでしょう?」
「……」
すずの不安の表情は和らぎ、微笑みが戻ってくる。
「分かったの、パパ。忠告有り難うなの」
「I don't come to fee.(礼には及びません)」
得意のネイティブイングリッシュで告げる鈴木さん。
「では忠告ついでにもうひとつ」
鈴木さんは、すずの胸元を指差す。
同時に、ハラリと落ちるすずのバスタオル。