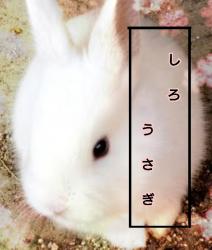「お互い仕方無くって形で決まった役だけど、凍堂さんが凄く頑張ってる姿見たらさ。
オレも頑張らなきゃって思えるんだ」
「そっ……それはその……
なったからには頑張らないとって……」
「そう思えることが凄いことだよ?」
緋彗くんの不意の何気ないそんな言葉が胸を静かに掻き乱す。
誰かにこうして真っ直ぐ認められることって……
少し恥ずかしくて心がくすぐったい。
「ま、まだまだだから……あたしなんて……!
とにかく文化祭までにキチンと出来るように……ですね、その……」
「……ふはは。
凍堂さんって意外とクールじゃないんだね」
「へ……?」
「いつも澄ました顔してたから」
からかうような口振りでクスッと笑う緋彗くん。
彼のこんな表情の笑みは初めて見た。
「なぁ……っ。
澄ましたつもりは無かったんだけどー……」
「冗談だってー。
そんな真剣に落ち込まないで?」
「何て言うか……緋彗くん天然S?」
「はは。なにそれー」
私の真剣な指摘も春風のような柔らかい笑みに流されてしまう。
「緋彗くんこそ澄ました顔してたよー」
「そう見えちゃうだけだよー。
オレ人見知りだからつい構えちゃうっていうか」
「……え。
あたしも……だよ」
「なんかオレら……似てるのかな」
何もかも……予想していなかったことの連続だ。
文化祭の劇のヒロインをやるなんて。
まさかのそのお相手が緋彗くんだなんて。
その彼と今自然と言葉を交わしているなんて。
「……あ。
セリフ覚えに関してはオレの方がちょっぴり優位かもね」
「……やっぱりS……!」
もちろん、澄ましたプリンスの意外なギャップに関しても。
人生とはいつ何が起きるのか分からないものですね…────────
*
あれから1週間が経った。
私のセリフ覚えが悪いのは相変わらず。
それでも緋彗くんの足を引っ張る訳にはいかない。
勉強時間と睡眠時間を削っての猛特訓。
そのご褒美とも言えるべき衣装が完成したようでウキウキとした足取りで緋彗くんが指定した場所まで向かっていた。
そんな貴重なはずのお昼休みの今……