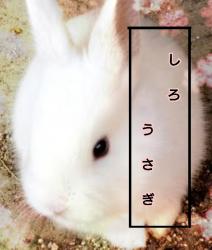いやいやいやいや。
違う、違うの、私が気にしているところはそんなことじゃないの。
「……や、やるしか……無いんだよね……」
何を考えているか到底見当もつかない緋彗くんの横顔を盗み見しながら、情けなく呟く私であった…────────
*
「……よろしく、緋彗くん」
よし……よしよし。
そこそこ決まったんじゃないか、凛。
こういうのは初めの滑り出しが大切だ。
ただでさえセリフを覚えるなんて苦手な作業なんだから、せめて雰囲気だけでも出来る女を醸し出さなきゃ……。
「うん。
よろしく、凍堂さん」
観察する限り緋彗くんは割りと大人しい性格で話も聞き役に徹していることが多い。
年上っぽい雰囲気を漂わせている。
かつクールに見られがちで、私も彼にクールな人だなぁという印象を抱いている。
それは今言葉を交わしても覆されることはなかった。
緋彗くんとはそれなりに話したことはあるもののこうして本格的に絡むのはこれが初めてだ。
「緋彗くんさすがモテるだけあって発表の時の歓声、凄かったね」
「素直に嬉しいことなんだけどさ、女の子のああいう声ってちょっと苦手なんだよねー」
台本を捲る指先を止めて、こちらに向きながら苦笑する緋彗くん。
「え、そうなんだ?
意外だなー。
でもちょっと分かるかも」
その緋彗くんの表情を見て、私も同じような顔をして返事をする。
こうして学校の王子と話しているなんてある意味夢のような時間だ。
そしてこれからその日常が少しばかり続いていくのだと思うと更に不思議な感覚だ。
とにかく……
王子の足を引っ張らないようにしなくては……
「え……えっと……ごめん。
次のセリフなんだっけ……」
相手にもガッカリさせるような思いはさせたくないのに……
「ここは魔女からのリンゴの押し売りをかわそうとするシーンだから?」
面倒くさいって思われたら……もうやっていけないのに……
「あ、あぁ……そうだった……!
えっと……
で、でも……ここを開けてはいけないと言われているんです……?」
「そうそう、そのセリフだよ」
「……あ、足……
引っ張っちゃってごめん……!」
私は何やってんのォォォォ!
なんでこんなセリフが頭に叩き込めないの……!
しかもなんで疑問系なの、そんなセリフ無いでしょ……私!!
「ちょ、ちょっと……一人で練習するね……
また明日……お願いできるかな……」
「オレでよかったらまだ付き合うよ?」
「で、でもそんな緋彗くんに悪いし……」
「そんなこと思わないでよ?」
そんな出来が悪いを超えて最悪な私にも緋彗くんは仏の如く微笑む。