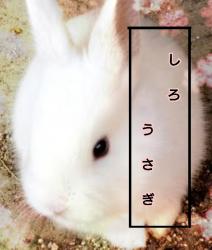非社交的な私には重すぎる任務……。
でも緋彗くんが居てくれると不思議と落ち着いてくる自分がいた。
約1ヶ月ちょっとほとんど毎日毎日一緒に練習して、一緒に帰って。
劇の配役が発表された運命の悪戯に今となっては感謝したい。
「凍堂さんなら大丈夫。
あんだけ練習したから!
ほら、オレを見てて」
大きな手が励ますように肩に一瞬触れて緋彗くんはステージへ。
本当にそれだけで上手く出来てしまうような気がした。
「頑張らなきゃ……!」
「あーあ。
衣装復活しちゃったんだー、つまんな」
「あ……っ。
やっぱり……」
「やっぱりってなにー?
証拠も無いのにまるであたしらがやったみたいな言い方してさー」
「あり得ないんですけどー」
意気込む私のもとへステージの袖まで上がって来たあの三人衆。
「てか緋彗くん相手にセリフ噛んだりしたら笑えないからさぁ」
「ま、そん時は馬鹿にしてあげるから~?」
「それアリ~!」
「……」
三人から逃げるようにステージの緋彗くんへ不意に視線を向ければ……
偶然にもセリフが無いタイミングの緋彗くんと合わさる視線。
それが少し心配そうにも見えて大丈夫だよという意味を込めて微笑んだ。
「……ちょっと何笑ってんの?」
「超余裕じゃん」
「あたしは……誰に何と言われても最後は……
自分自身を信じてあげたい」
「……あっそ。
別に興味無いし」