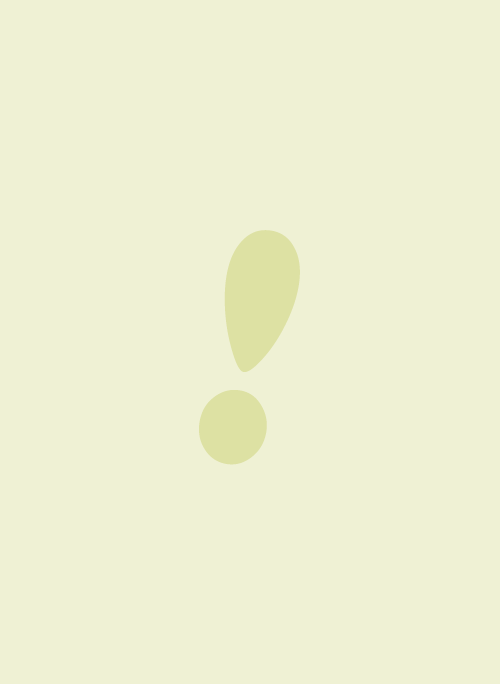あたし、どうなるんだろ……
このまま、授業が終わるまで誰にも気付いてもらえない?
本当にそうだったら、どうすればいい?
誰か。
誰でもいいから、助けて。
「……とう、じょ…」
「────……蘭?」
ふと顔を上げると、ボヤけた視界に写る誰かの姿。
誰?東條……?
あたしはギュッと、その人の首に腕をまわした。
フワリと香る、あたしの好きな香水の香り。
ああ、東條だ。
直感で、そう思った。
「お前……心配になって来てみたら‼
何でこんな状態で学校なんか来てんだよ!?」
ほんとに、東條が助けてくれたんだ……
「……ありが、と」
微かに出た声。
もう一度ギュッと腕に力を入れたところで、あたしは意識を手放した。
このまま、授業が終わるまで誰にも気付いてもらえない?
本当にそうだったら、どうすればいい?
誰か。
誰でもいいから、助けて。
「……とう、じょ…」
「────……蘭?」
ふと顔を上げると、ボヤけた視界に写る誰かの姿。
誰?東條……?
あたしはギュッと、その人の首に腕をまわした。
フワリと香る、あたしの好きな香水の香り。
ああ、東條だ。
直感で、そう思った。
「お前……心配になって来てみたら‼
何でこんな状態で学校なんか来てんだよ!?」
ほんとに、東條が助けてくれたんだ……
「……ありが、と」
微かに出た声。
もう一度ギュッと腕に力を入れたところで、あたしは意識を手放した。