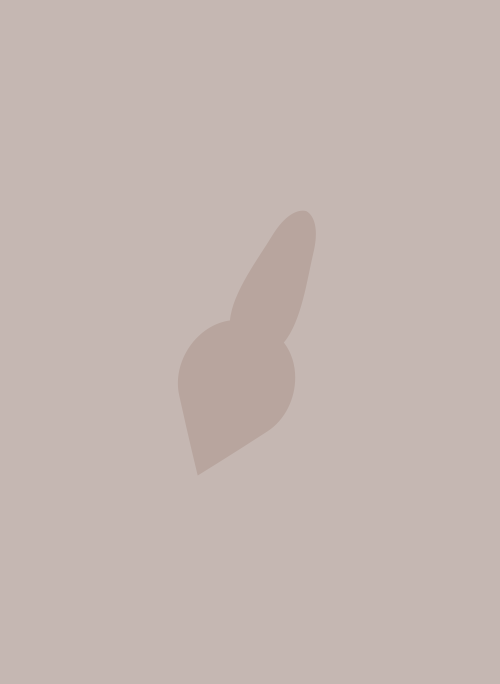『おい、待てよ。』
俊は何も気づいてなかったじゃない。
笑っちゃうよ、こんな切ない想いするんだって、恋は自由じゃなかったんだって。
そう必死になってる自分が虚しかった。
『なによ。』
掴んできた手を振り払い顔をあげた。
なんでそんな顔するの?
そう聞いてしまいそうなくらいの悲しい顔をした君は私に優しくキスをした。
そして、そっと頭を撫で、私に背を向け歩き始めた。
『なんで…』
とり残された私は苦しく悲しい思いで胸が痛くて息をするのが辛かった。
これが恋だったんだと気づいた時には、もう君の姿はどこにもなかった。
俊は何も気づいてなかったじゃない。
笑っちゃうよ、こんな切ない想いするんだって、恋は自由じゃなかったんだって。
そう必死になってる自分が虚しかった。
『なによ。』
掴んできた手を振り払い顔をあげた。
なんでそんな顔するの?
そう聞いてしまいそうなくらいの悲しい顔をした君は私に優しくキスをした。
そして、そっと頭を撫で、私に背を向け歩き始めた。
『なんで…』
とり残された私は苦しく悲しい思いで胸が痛くて息をするのが辛かった。
これが恋だったんだと気づいた時には、もう君の姿はどこにもなかった。