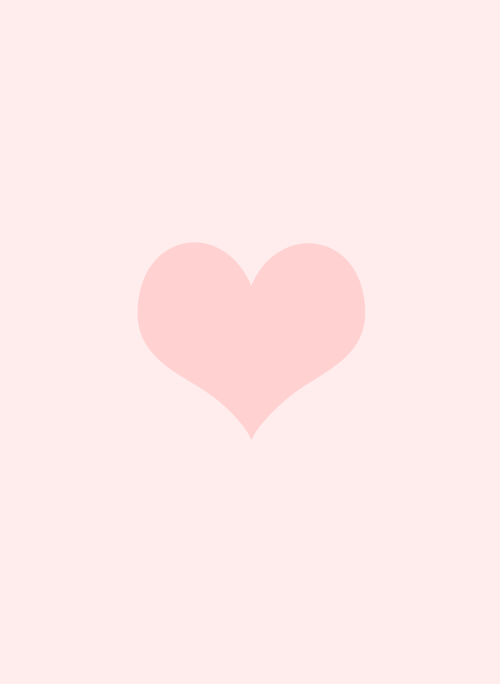「ねえ、大介。そんな隣の高校生ほっときなさいよ」
そんな声が聞こえてきて、大ちゃんの知り合いだと気づいた。
『大介』そう呼び捨てにする、ボルドーのルージュが奇麗に塗られた唇が弧を描いて妖艶に微笑んだ。
その人は、自分の手を大ちゃんの肩に乗せると何か耳元で囁いた。
その光景に、ドクンと胸が締め付けられる。
「仕方ないだろ……」
少し困ったような表情でその言葉が聞こえて、私は急に息苦しくなった。
苦しい……。
いつまでたっても私は大ちゃんに追いつけない。
その現実を目の前にして、頭が真っ白になった。
そんな声が聞こえてきて、大ちゃんの知り合いだと気づいた。
『大介』そう呼び捨てにする、ボルドーのルージュが奇麗に塗られた唇が弧を描いて妖艶に微笑んだ。
その人は、自分の手を大ちゃんの肩に乗せると何か耳元で囁いた。
その光景に、ドクンと胸が締め付けられる。
「仕方ないだろ……」
少し困ったような表情でその言葉が聞こえて、私は急に息苦しくなった。
苦しい……。
いつまでたっても私は大ちゃんに追いつけない。
その現実を目の前にして、頭が真っ白になった。