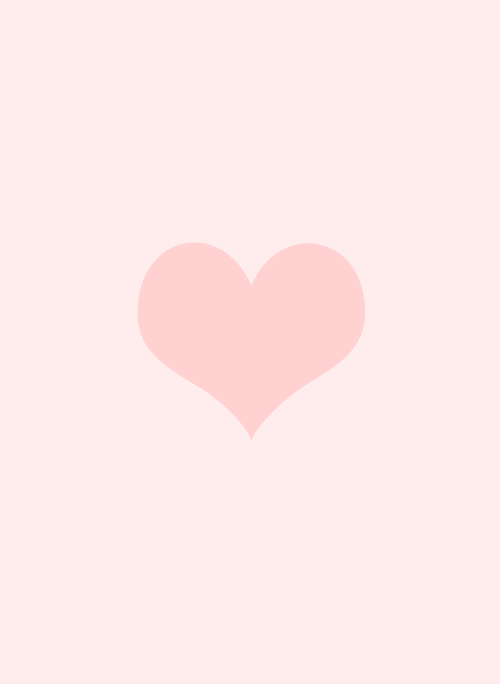剣道場の娘というからてっきりその影響だと思い込んでいたけれど違ったのか。
僕に憧れていた……いや、今でも僕に尊敬の念みたいなものを抱いているのだろう。だったら、会ったばかりの真夏の挙動不審も説明がつくような気がした。
でも、さぞ残念だったろうな。僕がこんな人間で。
「あの、あずさ」
意を決したような表情をして、真夏が僕に向き直る。
「本当に、あずさはわたしの、憧れなの。わたしお父さんに何度勧められても、剣道、絶対にやらなかったけど……あずさを見て、剣道ってこんなかっこいいんだ、すごいって、わたしもこんな風になりたいって……すごく、思ったの」
言葉をひとつひとつ丁寧に掬い上げるように言う真夏を、僕はまっすぐに見ることができなかった。そう、とだけ小さく返事をする。
「本当に、もう、剣道はしたくない?」
「……しないよ」
「絶対に?どうしてもどうしても、ダメ?」
すがるように迫る真夏を横目に、僕はぼんやりと考える。
彼女が僕に憧れたというのは、いつ、どこでの話だろう。自分も剣道を始めたいと思うほど彼女が憧れたのは、一体どの僕だろう。
表彰台のいちばん高いところが定位置だった僕?いつだって拍手の渦の中心にいた僕?それとも「天才」と褒め称えられ、いちばん綺麗なトロフィーを余すことなく自分のものにしていた僕?
君が求めているのは、どの僕だ?
どれにしたって、思いあたるその姿は全て今よりもずっと背が低く子どもの僕だ。声だって声変わりもしていない、男なのか女なのかよくわからないもの。