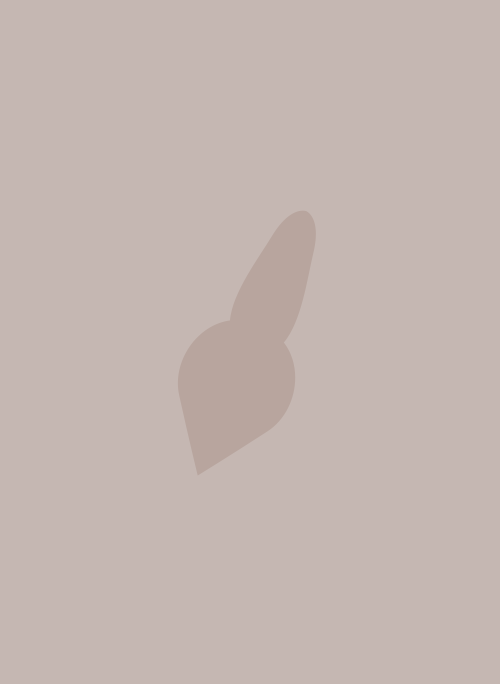どうしてだろう。
いつの間にか、目線が遠くを向いている。
そこには、やっぱり、あいつが座っているんだけど、私は納得できない。
好き、なんだろうか。
今のところ、そんな自覚はない。
しかし、魅かれる物はあるようだ。だって、そうじゃなきゃ、私が目を離せないことに理由がつかないから。
イットキノ、キノマヨイ。
どこからか頭に言葉が吸い込まれたように、そう思って、目を閉じた。
しばらくすると、まぶたの裏がウズウズしてくる。
嫌だと思っても、勝手に開いてしまう。
それでも、意識してれば大丈夫。
あいつを見ないように注意していれば、何の問題もない。
心苦しいなんてもちろん思わないし、むしろ、こうしていた方が気分良く過ごせる。他人、それもクラスメイトの男子なんかを、ジロジロ眺めるような人間だなんて、考えたくもない。
ーーーーー
「……ねえ、ナズっ。ナズったら」
「ん?………ああ、ネネか」
目の前に、心配そうな琴音の顔があった。
「どうしたの?何かあった?」
「?特に何も。どうしてそう思うの?」
「いや、だって、ナズがこんな風に寝てるの、初めてだもん。寝不足なの?それとも、グレた?」
それを聞くと、私は思わず吹き出してしまった。
ネネも狙って言ったんだろうけど、急に「グレた?」だって。
「いやいや、ぜーんぜんそういうのじゃないから」
「そう?」
「うん。気にしないで」
「ふーん………」
手をヒラヒラさせながら返すと、ネネは何を思ったか、私の耳元に口を寄せてきた。
「ねっ、タカフミのこと、さっきからチラッ、チラッて見てるでしょ」
「うぇっ?!」
「ふふふ、分かってんだからね」
バレていたのか。
それを全て見届けた上で寝不足かどうかなんて聞いてくるなんて、なかなかにサイテーだ。
「……、好き、なの?」
ネネはすっごく嬉しそうにニヤつきながら、周りを見渡して、すぐ近くに人がいないことを確かめる。
「…………違うし」
「うっそだぁ。まーたまた、恥ずかしがらなくても良いのにぃ。私、応援するよ」
「違うんだってば」
「うふふふ。そっか、違うのね」
「……うん」
ネネはまだ笑い足りないようで、ヒヒヒヒ、と喉を鳴らした。物語に出てくる魔女かよ、お前は。
「じゃあ何?好きでもない男の人を観察する趣味でもおありになるわけ?」
「…違うって言ってんのに」
私は机に横たえた自分の腕に頰を乗せたまま、ボソボソと喋る。なんか、まだ一教科も授業を受けてないのに疲れてきた。
「ん?まさかあれ?無自覚プレイを自分に強要してるの?」
「黙れーぃ」
私が顎をしゃくるように言うと、ネネはまたクスッと微笑んだ。
「…いやあ、ナズ先輩もマニアックになりましたねえ。私が育て上げてきた人材なのに、いつの間にかこっちが背中を追わなきゃいけなくなったか………」
「勝手に話を進めるな。しかも妙な方向に」
いつものことなので、のんびりと抗議する。
「えー、ナズぅ、ほんっとに自覚ナッシングなの?」
「うるさーい。さっさと自分の席に戻れ」
「だって、また朝の会まで時間あるし」
「健全な女子みたく読書でもしてろ」
「でもぅ、アタイ不良だしねぇ」
ネネはわざわざタバコを吸う真似までした。私はため息をつく。もう何を言っても無駄だろう。
「ほらほら、反対側を向いて寝なよ。タカフミに寝顔が見えるようにさあ」
「……………」
私が寝たふりをして浅い息を吸ったり吐いたりすると、ネネは肩をポンッと叩いて、
「よっ、青春してるねぇ」と語りかけてきた。
……………こんな面倒な青春なんか、要らない。
ーーーーー
(………ちぇっ、あのヤロー)
私は心の中で舌打ちする。
結局ネネは、私が言い返さないのをいいことに、好き勝手なことをベラベラ並べ上げて、担任が教室に入ってくるのと同時に自分の席へ帰って行った。
しかし、依然としてその影響は色濃く残っている。
余計にタカフミのことが気になり始めたのだ。
(私、これ、ガチで好きなのかな…?)
そう思うと焦ってくる。なぜ、なぜなんだ。どうして私はあいつを急に好いたんだ??!
(えっと、コケた時に手を差し伸べてくれた、り?)
我ながら貧相な思考に呆れて苦笑いした。
なんてったって、体力真っ盛りだということが象徴的な、華の14歳なんだよ?そうそう足を滑らせてたまるかってんだ。
優しい言葉をかけられたこともなし、そもそも中学校に上がってから男子と会話する機会なんて設けられるはずもなく。
(じゃあ理由がないじゃんかー!!!)
無自覚とかそれ以前に、取っ掛かりがないんだけど。脈なしとか、そういうことが言えるレベルにも達していない。
ネネは「それって運命ってやつぅ?キツく結ばれた赤い糸っ?!案外そういう入り口から進んだ方が恋愛って長続きするものなのよ!ひゅうひゅうっ!!」なんて言ってたけど、そうでもないと思う。つーか、テメーもまだ私と同い年のくせに恋愛論を確立してる風に喋ってんじゃねーよ。
……だから、説明がつかない。
胸がときめくわけでもなし、ただ、じっとあいつの顔を見つめてしまう。
怖いし、気持ち悪い。
なんだか自分の体じゃなくなったようで、ヘドが出そう……とまではいかないけど。
「今から、朝の会を、始めますっ、きりっつ!」
そんな日直の号令に合わせて、ガタガタと椅子を鳴らしながら、みんなが立てる。
「礼っ!」
「「「おはよーございます」」」
その挨拶に、私は参加しなかった。
他にも数人、全く口を動かしてない奴いるし。実際のトコ、ほとんどの人が口パクだし。
その時、とうとう、こっそりとあいつを横目で見てしまった。
……うん、あいつの顔だ。それ以外、特に何も思わない。笑顔でもなければ、悲しげでもないし、フツーな感じだね、あれは。
「着席!」
ガタンガタン
みんなが椅子に座ってからも、ごちゃごちゃ色んなことを規則的に言った後、担任の話になった。別に気に留めることでもないので、私はぼんやりと座っている。
「おーい、お前らぁ、こっち向けよ。鈴木、まだ寝るなよ。そんなことされたら、こっちが悲しくなるだろーーが!!」
みんなはウンザリと椅子の背もたれに体を預けていて、誰も鈴木の方すら向かない。どーせ鈴木もそんなことでは起きないだろうし。
「あれ、今のおもろくなかったか?…ん?やっぱ思春期だなぁ、お前らは。俺が何言ってもハートに響きやしないんだ。…あー、分かってるよ。『早く終われ』とか考えてんだろ?バッチリお見通しだぜ。でもさぁ、俺も教師って職業柄、そう易々とオッケーするわけにはいけないわけよ」
誰が聞いたわけでもないのに、身振り手振りを交えながら独りで喋り続ける。そんなこと思ってんなら、さっさと話を引き上げればいいのに。でも、これもいつものことだ。もう慣れた。
「じゃあ、あれだ。そんなメンドくさい年頃のお前達にはこれっ、恋バナをしてやるぞー。フゥッ!俺様、か、ん、だ、い!!」
(もう教師やめちまえよっ!)
思わずツッコむ。でも、表情にもそんなことは出さない。
「あー、あれだ、俺の初恋ってのはぁ、まだ小さい頃だった。今でも覚えてるぜ。米粒よりも小さな自分が………、ってそれ!まだ産まれてねえっつーの!わはははは!!」
(……………)
まさか、ギャグだと思っているのか?!今のその話を、ギャグだと信じているのか???!!!
私は思わず顔を上げた。
驚きで目も見開かれている。
「……おっ、大体の奴の視線がこのイケメンな俺の顔面に突き刺さってくるぜい。うー、人気者は辛いねぇ。…っと、ところで、俺が職員室から持ってきたこのプリント、誰だか配ってくれる人………、おいっ!どうしてみんな顔を下げる!!早く数人で良いから、…出て来いやっ!!」
最後の掛け声は、某格闘家の真似なのだろう。そんなことをしたところで、ノコノコ出て行く人もいない。コテンパンにされるのなんて嫌だからね。
「しっかたねーなー。職員室から全員分持ってくるだけで出血大サービス、いや、血は出てないから止血大サービスだってのに、誰も協力してくれねーのかぁ。冷たいクラスだな。冷房の電源を切ってやろうか」
そう言いつつも、担任はプリントをペラペラめくって、数枚取り出し、列の最初の人に渡す。
すると、その人達は渋々自分のを一枚引き抜いて、残りを後ろに回していくのだ。
「…俺だってなー、こんな効果あるのかないのか分かんない宣伝ポスターを配りたいわけねぇよ。できれば紙飛行機にして窓から放り出したいくらいだ。でも、これをサボってると俺は………、っておい!マジに紙飛行機を折るなって!やめろっ!窓はダメだっ!後始末しなきゃいけなくなるからっ!!」
担任が一人の生徒を捕まえている間に、他のみんなは動き始める。もう話はとっくに終わっているのだ。だけど、毎日、こんな感じで境界が曖昧になって終わる。
そして、すぐに。
「…ナーズっ」
はあ、またかよ。私がちらりと目をやると、ネネとみっちゃんが立っている。なんで増えてんだよ。
「ね、タカフミのどこが好きなのー?」
「うるさいよ、みっちゃんも」
「気になるもん!あのムサい男のどこが良いのかっ!!」
「ちょっと、みっちゃんってば、ナズの旦那にそれは言い過ぎでしょ」
「あはっ、ごめん」
…どーでも良いから、どっか行け。
私は、やはり無言で、二人を呪った。
タカフミ、か。
そう思った刹那、当のあいつが目の前を通って行った。
「はうっ!」
不覚にも、そんな声を出した私を、二人が顔を見合わせて笑っている。
いつの間にか、目線が遠くを向いている。
そこには、やっぱり、あいつが座っているんだけど、私は納得できない。
好き、なんだろうか。
今のところ、そんな自覚はない。
しかし、魅かれる物はあるようだ。だって、そうじゃなきゃ、私が目を離せないことに理由がつかないから。
イットキノ、キノマヨイ。
どこからか頭に言葉が吸い込まれたように、そう思って、目を閉じた。
しばらくすると、まぶたの裏がウズウズしてくる。
嫌だと思っても、勝手に開いてしまう。
それでも、意識してれば大丈夫。
あいつを見ないように注意していれば、何の問題もない。
心苦しいなんてもちろん思わないし、むしろ、こうしていた方が気分良く過ごせる。他人、それもクラスメイトの男子なんかを、ジロジロ眺めるような人間だなんて、考えたくもない。
ーーーーー
「……ねえ、ナズっ。ナズったら」
「ん?………ああ、ネネか」
目の前に、心配そうな琴音の顔があった。
「どうしたの?何かあった?」
「?特に何も。どうしてそう思うの?」
「いや、だって、ナズがこんな風に寝てるの、初めてだもん。寝不足なの?それとも、グレた?」
それを聞くと、私は思わず吹き出してしまった。
ネネも狙って言ったんだろうけど、急に「グレた?」だって。
「いやいや、ぜーんぜんそういうのじゃないから」
「そう?」
「うん。気にしないで」
「ふーん………」
手をヒラヒラさせながら返すと、ネネは何を思ったか、私の耳元に口を寄せてきた。
「ねっ、タカフミのこと、さっきからチラッ、チラッて見てるでしょ」
「うぇっ?!」
「ふふふ、分かってんだからね」
バレていたのか。
それを全て見届けた上で寝不足かどうかなんて聞いてくるなんて、なかなかにサイテーだ。
「……、好き、なの?」
ネネはすっごく嬉しそうにニヤつきながら、周りを見渡して、すぐ近くに人がいないことを確かめる。
「…………違うし」
「うっそだぁ。まーたまた、恥ずかしがらなくても良いのにぃ。私、応援するよ」
「違うんだってば」
「うふふふ。そっか、違うのね」
「……うん」
ネネはまだ笑い足りないようで、ヒヒヒヒ、と喉を鳴らした。物語に出てくる魔女かよ、お前は。
「じゃあ何?好きでもない男の人を観察する趣味でもおありになるわけ?」
「…違うって言ってんのに」
私は机に横たえた自分の腕に頰を乗せたまま、ボソボソと喋る。なんか、まだ一教科も授業を受けてないのに疲れてきた。
「ん?まさかあれ?無自覚プレイを自分に強要してるの?」
「黙れーぃ」
私が顎をしゃくるように言うと、ネネはまたクスッと微笑んだ。
「…いやあ、ナズ先輩もマニアックになりましたねえ。私が育て上げてきた人材なのに、いつの間にかこっちが背中を追わなきゃいけなくなったか………」
「勝手に話を進めるな。しかも妙な方向に」
いつものことなので、のんびりと抗議する。
「えー、ナズぅ、ほんっとに自覚ナッシングなの?」
「うるさーい。さっさと自分の席に戻れ」
「だって、また朝の会まで時間あるし」
「健全な女子みたく読書でもしてろ」
「でもぅ、アタイ不良だしねぇ」
ネネはわざわざタバコを吸う真似までした。私はため息をつく。もう何を言っても無駄だろう。
「ほらほら、反対側を向いて寝なよ。タカフミに寝顔が見えるようにさあ」
「……………」
私が寝たふりをして浅い息を吸ったり吐いたりすると、ネネは肩をポンッと叩いて、
「よっ、青春してるねぇ」と語りかけてきた。
……………こんな面倒な青春なんか、要らない。
ーーーーー
(………ちぇっ、あのヤロー)
私は心の中で舌打ちする。
結局ネネは、私が言い返さないのをいいことに、好き勝手なことをベラベラ並べ上げて、担任が教室に入ってくるのと同時に自分の席へ帰って行った。
しかし、依然としてその影響は色濃く残っている。
余計にタカフミのことが気になり始めたのだ。
(私、これ、ガチで好きなのかな…?)
そう思うと焦ってくる。なぜ、なぜなんだ。どうして私はあいつを急に好いたんだ??!
(えっと、コケた時に手を差し伸べてくれた、り?)
我ながら貧相な思考に呆れて苦笑いした。
なんてったって、体力真っ盛りだということが象徴的な、華の14歳なんだよ?そうそう足を滑らせてたまるかってんだ。
優しい言葉をかけられたこともなし、そもそも中学校に上がってから男子と会話する機会なんて設けられるはずもなく。
(じゃあ理由がないじゃんかー!!!)
無自覚とかそれ以前に、取っ掛かりがないんだけど。脈なしとか、そういうことが言えるレベルにも達していない。
ネネは「それって運命ってやつぅ?キツく結ばれた赤い糸っ?!案外そういう入り口から進んだ方が恋愛って長続きするものなのよ!ひゅうひゅうっ!!」なんて言ってたけど、そうでもないと思う。つーか、テメーもまだ私と同い年のくせに恋愛論を確立してる風に喋ってんじゃねーよ。
……だから、説明がつかない。
胸がときめくわけでもなし、ただ、じっとあいつの顔を見つめてしまう。
怖いし、気持ち悪い。
なんだか自分の体じゃなくなったようで、ヘドが出そう……とまではいかないけど。
「今から、朝の会を、始めますっ、きりっつ!」
そんな日直の号令に合わせて、ガタガタと椅子を鳴らしながら、みんなが立てる。
「礼っ!」
「「「おはよーございます」」」
その挨拶に、私は参加しなかった。
他にも数人、全く口を動かしてない奴いるし。実際のトコ、ほとんどの人が口パクだし。
その時、とうとう、こっそりとあいつを横目で見てしまった。
……うん、あいつの顔だ。それ以外、特に何も思わない。笑顔でもなければ、悲しげでもないし、フツーな感じだね、あれは。
「着席!」
ガタンガタン
みんなが椅子に座ってからも、ごちゃごちゃ色んなことを規則的に言った後、担任の話になった。別に気に留めることでもないので、私はぼんやりと座っている。
「おーい、お前らぁ、こっち向けよ。鈴木、まだ寝るなよ。そんなことされたら、こっちが悲しくなるだろーーが!!」
みんなはウンザリと椅子の背もたれに体を預けていて、誰も鈴木の方すら向かない。どーせ鈴木もそんなことでは起きないだろうし。
「あれ、今のおもろくなかったか?…ん?やっぱ思春期だなぁ、お前らは。俺が何言ってもハートに響きやしないんだ。…あー、分かってるよ。『早く終われ』とか考えてんだろ?バッチリお見通しだぜ。でもさぁ、俺も教師って職業柄、そう易々とオッケーするわけにはいけないわけよ」
誰が聞いたわけでもないのに、身振り手振りを交えながら独りで喋り続ける。そんなこと思ってんなら、さっさと話を引き上げればいいのに。でも、これもいつものことだ。もう慣れた。
「じゃあ、あれだ。そんなメンドくさい年頃のお前達にはこれっ、恋バナをしてやるぞー。フゥッ!俺様、か、ん、だ、い!!」
(もう教師やめちまえよっ!)
思わずツッコむ。でも、表情にもそんなことは出さない。
「あー、あれだ、俺の初恋ってのはぁ、まだ小さい頃だった。今でも覚えてるぜ。米粒よりも小さな自分が………、ってそれ!まだ産まれてねえっつーの!わはははは!!」
(……………)
まさか、ギャグだと思っているのか?!今のその話を、ギャグだと信じているのか???!!!
私は思わず顔を上げた。
驚きで目も見開かれている。
「……おっ、大体の奴の視線がこのイケメンな俺の顔面に突き刺さってくるぜい。うー、人気者は辛いねぇ。…っと、ところで、俺が職員室から持ってきたこのプリント、誰だか配ってくれる人………、おいっ!どうしてみんな顔を下げる!!早く数人で良いから、…出て来いやっ!!」
最後の掛け声は、某格闘家の真似なのだろう。そんなことをしたところで、ノコノコ出て行く人もいない。コテンパンにされるのなんて嫌だからね。
「しっかたねーなー。職員室から全員分持ってくるだけで出血大サービス、いや、血は出てないから止血大サービスだってのに、誰も協力してくれねーのかぁ。冷たいクラスだな。冷房の電源を切ってやろうか」
そう言いつつも、担任はプリントをペラペラめくって、数枚取り出し、列の最初の人に渡す。
すると、その人達は渋々自分のを一枚引き抜いて、残りを後ろに回していくのだ。
「…俺だってなー、こんな効果あるのかないのか分かんない宣伝ポスターを配りたいわけねぇよ。できれば紙飛行機にして窓から放り出したいくらいだ。でも、これをサボってると俺は………、っておい!マジに紙飛行機を折るなって!やめろっ!窓はダメだっ!後始末しなきゃいけなくなるからっ!!」
担任が一人の生徒を捕まえている間に、他のみんなは動き始める。もう話はとっくに終わっているのだ。だけど、毎日、こんな感じで境界が曖昧になって終わる。
そして、すぐに。
「…ナーズっ」
はあ、またかよ。私がちらりと目をやると、ネネとみっちゃんが立っている。なんで増えてんだよ。
「ね、タカフミのどこが好きなのー?」
「うるさいよ、みっちゃんも」
「気になるもん!あのムサい男のどこが良いのかっ!!」
「ちょっと、みっちゃんってば、ナズの旦那にそれは言い過ぎでしょ」
「あはっ、ごめん」
…どーでも良いから、どっか行け。
私は、やはり無言で、二人を呪った。
タカフミ、か。
そう思った刹那、当のあいつが目の前を通って行った。
「はうっ!」
不覚にも、そんな声を出した私を、二人が顔を見合わせて笑っている。