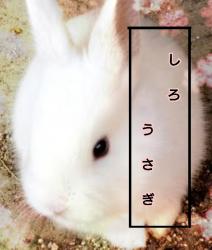*
大勢の人が入り乱れる外の世界は多くの色で混じり、いつしかくすんだ灰色になっていた。
─────────…でも。
優哉のいるこの空間は違った。
誰にも干渉されず透明で……
「おはよ、優哉」
「本当に……ちゃんと覚えてたんだな!」
「何よーその馬鹿にした口調はっ」
「馬鹿にしてねー!
嬉しいんだよっ」
そこにいるのが心地良かった。
この人の隣にずっといられたら……
いつしかそんなことを考える時間が増えていた。
「はい、あとこれ優哉が食べたがってたスイカ」
「えっ、え!?
食べていいのか……?」
「もちろん?
なんでそんな疑わしげな顔してるのー?」
なんだかその優哉の表情が面白くて緩んでしまう口元。
「な、なんか……凛がオレに気を遣い過ぎてて気持ち悪い!」
「……えらくハッキリ言ってくれるものねー?
じゃあスイカはあたしが貰……」
「ダメだダメだぁ!
このスイカはもうオレのもんだ!
仕方無いから一口やるぜー?」
「はぁ。
ったくー、相変わらず元気すぎ」
結局二人で半分こしたスイカは元からそんなに量が無かったためにすぐに食べきってしまった。
それから優哉はまた写真が見たいと言い出して。
真っ白なベッドのシーツに広げる写真の数々がより存在感を示す。
「あ!
この写真いつまで持ってるつもりだよー?
恥ずかしーじゃん」
「これはあたしのお気に入りだから残しとくのっ」
優哉が言っているのは初めて優哉を映した写真のこと。
本人はあまり気に入っていないらしくいつもこれを見つけては文句をつける。
「だってオレこれ服も部屋も真っ白でなんか顔だけ浮いてて気持ち悪いし!」
「ははっ。
言われてみれば確かにそうだね~?」
初めて会ったのがいつも私が写真を飾りにいく部屋だ。
ホワイトボードを眺める優哉の横顔を勝手に撮った、その時の写真だ。
「この頃の優哉は尖ってたっていうか無気力だったよね」
今からは想像しにくいかも知れないがこう見えてものすごーく人見知りな優哉は……
出会った頃はまるで私を敵と見なすかのような凍った視線を投げ付けられたものだ。
「あー、あの時か。
あんまり思い出したくねーかな」
苦笑する優哉も当時のことは気の迷いだとか何とか言っていた。
「そんな優哉とまさかここまで仲良くなれるとは。
人生分かんないもんだね」
「だな。
オレ……もう死んでもいいって……思ってた。
凛と凛の撮った写真に出会うまでは……」
「えっ……?」
「毎日必死な顔して生きてく自分が醜く映った気がしてさ。
それがすごい虚しかった。
それならいっそのこと早く死ねれば……って」