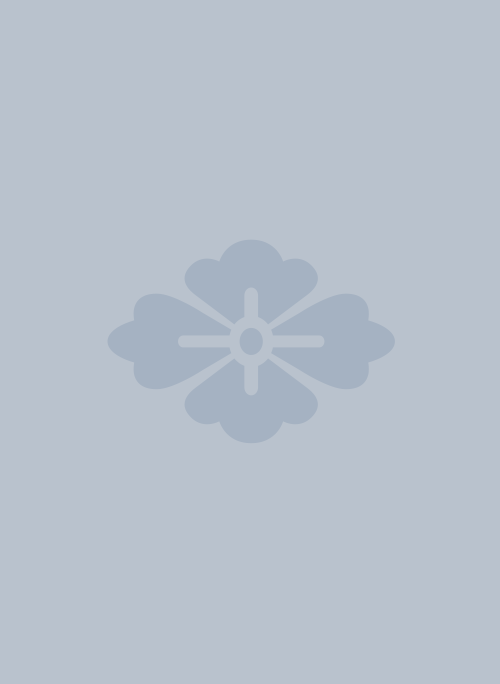絶望する久光に与えられた仕事は、邸の大君である姫君のお相手だった。
その姫君こそが、琴乃の姫君であった。
初め、久光は姫君のことを「姫様」と呼ぶのに違和感を感じていた。
彼が「様」とつけていた人は、祖父母くらいだった。
姫君のお相手と雑用とと、慣れない仕事ばかり。
兄君譲りの立派な衣裳以外は、全てが朽ちていた。
勿論、彼の心も。
「昔のように振舞ってはなりません。よろしいですか。」
乳母は、久光にそう聞かせていたが、本当は、そんなことは言いたくなかった。
その姫君こそが、琴乃の姫君であった。
初め、久光は姫君のことを「姫様」と呼ぶのに違和感を感じていた。
彼が「様」とつけていた人は、祖父母くらいだった。
姫君のお相手と雑用とと、慣れない仕事ばかり。
兄君譲りの立派な衣裳以外は、全てが朽ちていた。
勿論、彼の心も。
「昔のように振舞ってはなりません。よろしいですか。」
乳母は、久光にそう聞かせていたが、本当は、そんなことは言いたくなかった。