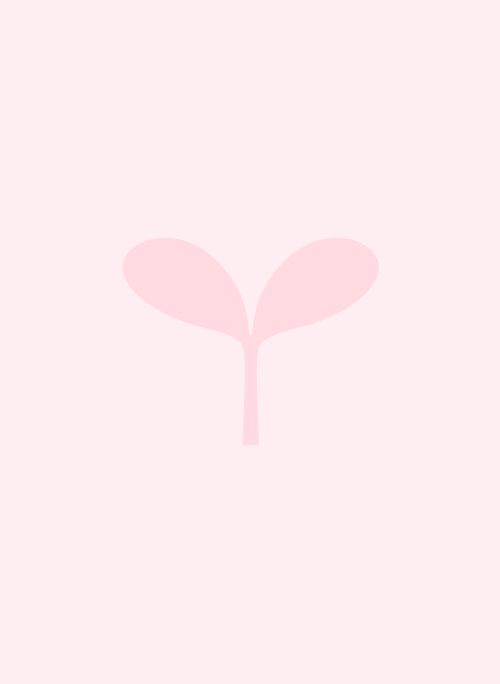「なんか今日の夕輝、変」
両の人差し指がせわしなく髪を巻き付けている。
「変とは何だ」
「だって変じゃん! なんか……優しいし」
「お前、俺がいつもは優しくないみたいに……」
本当はもっと早く、こんな風に本音で向き合うべきだったのかもしれない。
そうしたら今胸にある微かに苦い後悔もなくなっていただろう。
そっぽを向いて突っぱねてきたけれど、透花が変だと言った優しさで、俺はずっとこの幼馴染のことを見つめてきたのだから。
「気分とか悪くないか?」
「うん、平気」
「ここはちょっと暑いな。日陰に行こう」
階段室の裏側にまわりこんで、そこに伸びる影に腰を下ろす。
ひんやりとしたコンクリートの壁に寄りかかれば、ここからはもう柵の向こうの景色は見えなくて、ただ青い空だけが俺達の目の前に広がっていた。
「あのね、夕輝……ごめんね」
透花の小さな声が鼓膜にふるふると震える。
「私のわがままで夕輝まで付き合わせちゃって。夕輝のこと、巻き込んじゃった。ごめんね」
「別に……お前のわがままに付き合わされるのなんて今に始まったことじゃないだろ。それに俺はここにいたいからいるだけだ。だから気にすんな」
間に置かれた二人の指先が微かに触れる。
俺はそちらを見ないまま――どちらともなく温もりを探り合って、指を絡めるとそのままぎゅっと握りしめた。
両の人差し指がせわしなく髪を巻き付けている。
「変とは何だ」
「だって変じゃん! なんか……優しいし」
「お前、俺がいつもは優しくないみたいに……」
本当はもっと早く、こんな風に本音で向き合うべきだったのかもしれない。
そうしたら今胸にある微かに苦い後悔もなくなっていただろう。
そっぽを向いて突っぱねてきたけれど、透花が変だと言った優しさで、俺はずっとこの幼馴染のことを見つめてきたのだから。
「気分とか悪くないか?」
「うん、平気」
「ここはちょっと暑いな。日陰に行こう」
階段室の裏側にまわりこんで、そこに伸びる影に腰を下ろす。
ひんやりとしたコンクリートの壁に寄りかかれば、ここからはもう柵の向こうの景色は見えなくて、ただ青い空だけが俺達の目の前に広がっていた。
「あのね、夕輝……ごめんね」
透花の小さな声が鼓膜にふるふると震える。
「私のわがままで夕輝まで付き合わせちゃって。夕輝のこと、巻き込んじゃった。ごめんね」
「別に……お前のわがままに付き合わされるのなんて今に始まったことじゃないだろ。それに俺はここにいたいからいるだけだ。だから気にすんな」
間に置かれた二人の指先が微かに触れる。
俺はそちらを見ないまま――どちらともなく温もりを探り合って、指を絡めるとそのままぎゅっと握りしめた。