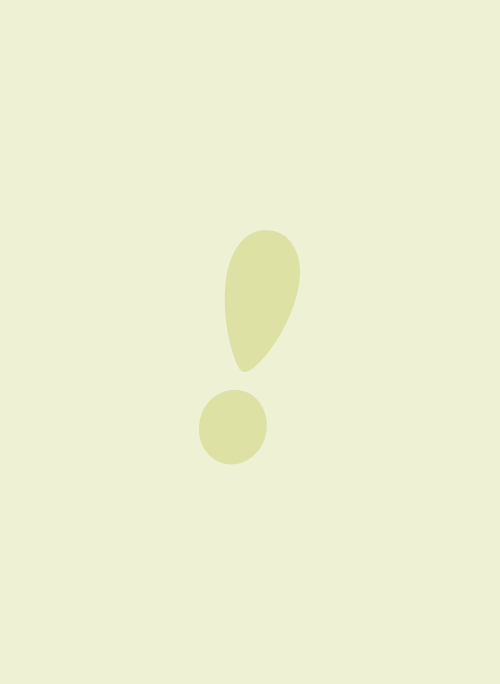『思い切って告っちゃえば?』
瑞穂が言った言葉が、頭の中でグルグルと回っている。
私は帰宅後、自宅の2階にある自分の部屋のベッドにゴロンと横になりながら、何度も何度も瑞穂の言葉を思い返していた。
正直、相葉先生に伝えてしまいたいっていう気持ちはある。
言ってしまえば楽になれるのかもしれない。
もしかしたら、相葉先生も私の気持ちを受け入れてくれるのかもしれない。
でも、もしも断られたら…?
相葉先生は今まで以下の接し方になってしまうんじゃないかと思うと、私はとても怖かった。
今よりも距離を感じるのなんて嫌だから…。
「どうしよう…。」
この一歩を踏み出さなかったら何も変わらない。
今よりも“良く”も“悪く”もならない―…
「どうしよ…。」
同じ考えの繰り返しに、もう何度目か分からない程の“どうしよう”という独り言を呟いていた。
すると、
「さくー!梢ちゃんから電話よー!」
1階にいる母からの呼びかけに、
「はぁーい。」
私は返事をしてからムクッと起き上がると、自分の部屋にある電話の子機を取った。
「もしもし?」
「あっ、さく?私、梢。」
いつものように話し始めた梢に、私は何だかほっとしていた。
「うん、どうしたの?」
私はもう一度ベッドに戻り、クッションを背中と壁の間にあてて座った。
「さく、悩んでるんじゃないかと思って。」
「えっ?」
「瑞穂が“告っちゃえば”なんて言ってたじゃない?だから。」
「ああ…。」
余りにも見事に言い当てられて、私は何て返せば良いかも分からずに言葉を失った。
「…その様子だと図星でしょ?」
そう言って、梢はいたずらっぽく笑った。
「うん…考えてた。ずっと考えてたよ。」
私は思わず“ヘヘッ”と照れ笑いをした。
瑞穂が言った言葉が、頭の中でグルグルと回っている。
私は帰宅後、自宅の2階にある自分の部屋のベッドにゴロンと横になりながら、何度も何度も瑞穂の言葉を思い返していた。
正直、相葉先生に伝えてしまいたいっていう気持ちはある。
言ってしまえば楽になれるのかもしれない。
もしかしたら、相葉先生も私の気持ちを受け入れてくれるのかもしれない。
でも、もしも断られたら…?
相葉先生は今まで以下の接し方になってしまうんじゃないかと思うと、私はとても怖かった。
今よりも距離を感じるのなんて嫌だから…。
「どうしよう…。」
この一歩を踏み出さなかったら何も変わらない。
今よりも“良く”も“悪く”もならない―…
「どうしよ…。」
同じ考えの繰り返しに、もう何度目か分からない程の“どうしよう”という独り言を呟いていた。
すると、
「さくー!梢ちゃんから電話よー!」
1階にいる母からの呼びかけに、
「はぁーい。」
私は返事をしてからムクッと起き上がると、自分の部屋にある電話の子機を取った。
「もしもし?」
「あっ、さく?私、梢。」
いつものように話し始めた梢に、私は何だかほっとしていた。
「うん、どうしたの?」
私はもう一度ベッドに戻り、クッションを背中と壁の間にあてて座った。
「さく、悩んでるんじゃないかと思って。」
「えっ?」
「瑞穂が“告っちゃえば”なんて言ってたじゃない?だから。」
「ああ…。」
余りにも見事に言い当てられて、私は何て返せば良いかも分からずに言葉を失った。
「…その様子だと図星でしょ?」
そう言って、梢はいたずらっぽく笑った。
「うん…考えてた。ずっと考えてたよ。」
私は思わず“ヘヘッ”と照れ笑いをした。