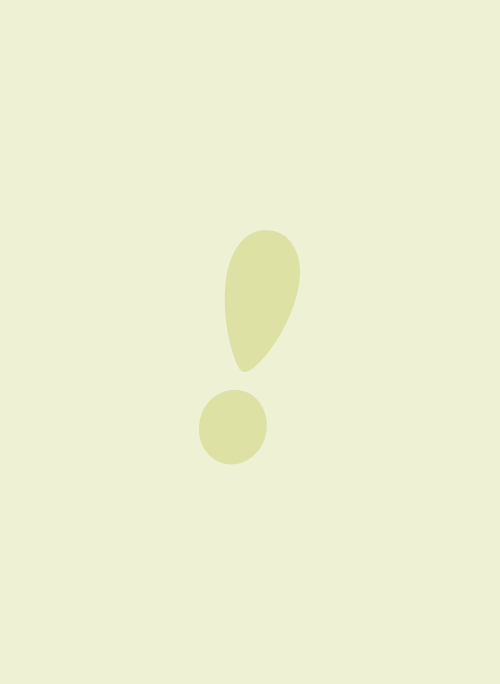『きっと傷つけた。私は大好きな人を傷つけたんだ…。』
怒りや悲しみや後悔を感じながら無我夢中で歩いていると、
「さく?」
「おかえりー。」
ロビーで待っていた瑞穂と梢に声をかけられて我に返った。
「ごめ…」
「…何かあったの…?」
口を開きかけた私の表情を見て、何かを悟ったのだろう。
心配そうに揺れる瞳で、瑞穂と梢が私を見ている。
私は何度この二人に心配をかけただろうか。
何度励まされただろうか。
そしてまた…。
「私…先生を…」
そう言って、私は両手で顔を覆って俯いた。
この時私の心を占めていたのは、嘘をつかれた事ではなく、
“きっと相葉先生を傷つけた”
という、罪悪感でいっぱいだった。
「…先生を傷つけた…。」
そう言って泣き出した私を、
「さく…。」
二人が心配そうに、両端から私の肩を抱いた。
何も理由も無くそんな事が起こるなんて、二人だって思っていなかっただろう。
「とにかく出よう。」
二人に支えられるように下駄箱に向かい、学校を後にした。
こんなはずじゃなかったんだ。
先生を傷つけるつもりはなかったんだ。
卒業まで残り僅かになっているのに、
大崎先生との事を見て見ぬ振りが出来なかった幼い自分。
冷静を保てなかった自分。
その全てが後悔と不安になり、
『相葉先生に嫌われたんじゃないか』
という想いで、一杯だった。
怒りや悲しみや後悔を感じながら無我夢中で歩いていると、
「さく?」
「おかえりー。」
ロビーで待っていた瑞穂と梢に声をかけられて我に返った。
「ごめ…」
「…何かあったの…?」
口を開きかけた私の表情を見て、何かを悟ったのだろう。
心配そうに揺れる瞳で、瑞穂と梢が私を見ている。
私は何度この二人に心配をかけただろうか。
何度励まされただろうか。
そしてまた…。
「私…先生を…」
そう言って、私は両手で顔を覆って俯いた。
この時私の心を占めていたのは、嘘をつかれた事ではなく、
“きっと相葉先生を傷つけた”
という、罪悪感でいっぱいだった。
「…先生を傷つけた…。」
そう言って泣き出した私を、
「さく…。」
二人が心配そうに、両端から私の肩を抱いた。
何も理由も無くそんな事が起こるなんて、二人だって思っていなかっただろう。
「とにかく出よう。」
二人に支えられるように下駄箱に向かい、学校を後にした。
こんなはずじゃなかったんだ。
先生を傷つけるつもりはなかったんだ。
卒業まで残り僅かになっているのに、
大崎先生との事を見て見ぬ振りが出来なかった幼い自分。
冷静を保てなかった自分。
その全てが後悔と不安になり、
『相葉先生に嫌われたんじゃないか』
という想いで、一杯だった。