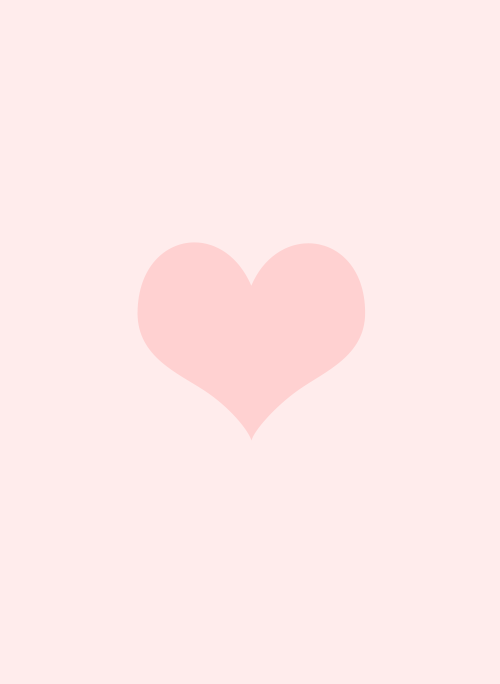その予感は不運にも的中し、やたら綺麗な肌をした美女は、寺島さんを見つけると顔を綻ばせた。
「寺島くん…?」
「えっと、うん。寺島です」
頬が緩んでるぞ、寺島。
「すごい偶然!コンビニでバイトしてるのは知ってたけど、大学から結構遠いところなんだね!」
「うん。家から近いから」
「そっか」
こちらの女性は存じ上げませんが、二人から漂う淡い桃色のオーラでわかってしまう。
寺島さんの好きな人だ。
あまり会話したことがないと溜息ばかり吐いていた寺島さんは、別人のように落ち着いた口調で話し、仲睦まじそうに笑い声を弾ませている。
なーにが脈なしだ。
どこからどうみても両想いじゃん。
まあどうせ、寺島さんのことだから彼女から好かれていることに気づけていないんだろうとは思っていたけど、あたしからしてみればちっとも面白くない。
「寺島さん」
「へ、あ、はい」
「勤務中」
「………すいません」
ふんと顔を逸らすと、元気を失った寺島さんが、美女に「ごめん」と謝るのが聞こえる。
しばらくして買い物を終えた美女が、寂しそうな表情で帰っていく。
その華奢な背中に、心の中で全力のあっかんべーをしてやった。