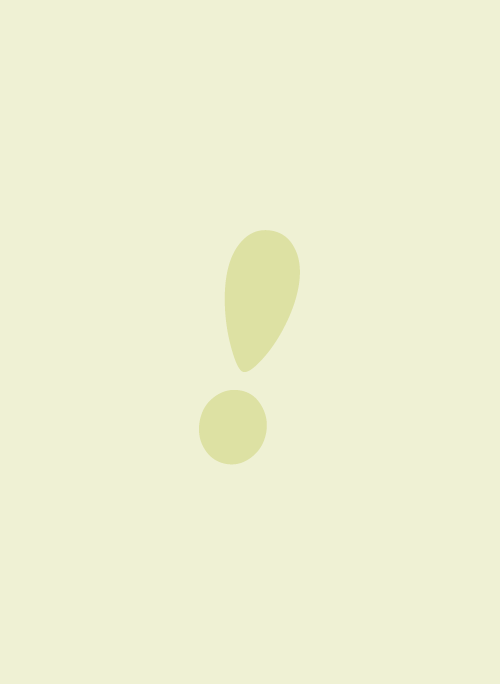着いた時には、水澄はか細い息で意識も無いような状態だった。
「っ!水澄…。水澄ぃ!」
僕から溢れた涙は、もう止まることを知らなかった。
「たくさん話かけてあげてください。
気持ちは、通じるんですよ。」
看護師はそう言った。
信じようとは思わなかったのに、
気付けば僕は水澄の手を握りしめてこう言っていた。
「好きだ。水澄。死ぬなっ!お願いだ…」
「光くん…。私も大好きなんだから…。」
「水澄っ!? 水澄っ!?
なぁっ、死ぬなよ…。」
「私ね、一つだけ心残りがあるの…。
名前に意味がほしかった…。
そしたら、もっと希望を持って生きれた気がするの…。」
「そんなっっ!」
「そんなこと…あるの。
ありがとう。光くん。」
「死なないでよ。死ぬなよ水澄!!」
僕の叫びも虚しく、白い病室にそれは響いただけだった。
水澄のそばにあった花瓶の花は、いつしかガクだけになって、季節は巡った。
「っ!水澄…。水澄ぃ!」
僕から溢れた涙は、もう止まることを知らなかった。
「たくさん話かけてあげてください。
気持ちは、通じるんですよ。」
看護師はそう言った。
信じようとは思わなかったのに、
気付けば僕は水澄の手を握りしめてこう言っていた。
「好きだ。水澄。死ぬなっ!お願いだ…」
「光くん…。私も大好きなんだから…。」
「水澄っ!? 水澄っ!?
なぁっ、死ぬなよ…。」
「私ね、一つだけ心残りがあるの…。
名前に意味がほしかった…。
そしたら、もっと希望を持って生きれた気がするの…。」
「そんなっっ!」
「そんなこと…あるの。
ありがとう。光くん。」
「死なないでよ。死ぬなよ水澄!!」
僕の叫びも虚しく、白い病室にそれは響いただけだった。
水澄のそばにあった花瓶の花は、いつしかガクだけになって、季節は巡った。