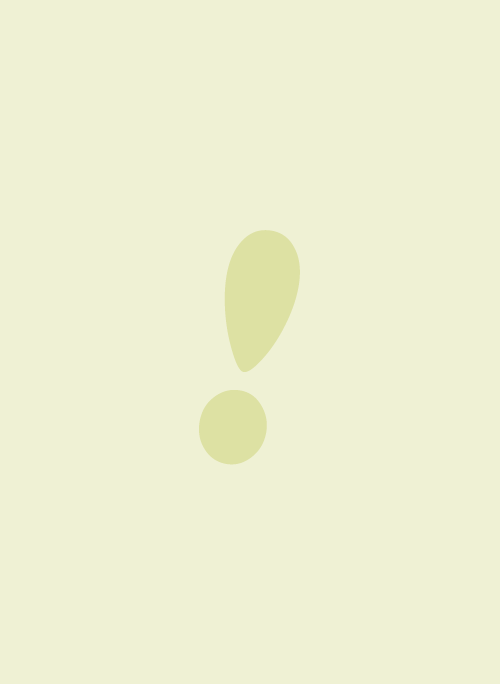その涙は暫く止むことはなかった。
泣きながら雑炊を頬張った。
どうして自分が泣いているのか、よくわからない私だが、男性はそばに居てずっと頭を撫でてくれていた。
「泣くほど美味しかった?」
雑炊を食べ終わる頃、私の目は充血し、パンパンに腫れてしまっていた。
こんな顔では、誰も私を『可愛い、綺麗』などと褒めてはくれないだろう。
現に、目の前の男性は泣き止んだ私の顔を見て「酷い顔」と笑った。
「確認しても良い?」
少し落ち着いてきたところで、初めてはっきりと口を開いた。
男性は私と向き合うように床に胡座をかいて座っている。
私はベッドに腰掛けている状態のため、どうしても男性よりも目線が高くなる。
これは失礼かと、男性の目線に合わせるよう、私も床に正座をする。
「私を助けてくれたのはあなただよね?」
「これが助けるってことになったのかは知らないけど、ここに連れてきたのは俺だね」
「……ありがとう」
感謝を述べるが、正直特に有難いとは思っていなかった。
あのまま体が冷え切った状態で放って置かれれば、私はもしかしたら今頃死んでしまっていたかもしれない。
けれどそれでも良いと思っていた。
母に必要とされないのならば、私は生きている意味がない。
自分の名前も、体も、心も、何も意味を持たない。
「ありがとうって顔じゃないよね」
「え?」
「ちっとも嬉しそうな顔じゃない」
男性は鋭く、私の心を見透かすようだった。
なんだか気まずくなり、私は男性から目を逸らす。
それでも男性は真っ直ぐに私を見つめていた。
泣きながら雑炊を頬張った。
どうして自分が泣いているのか、よくわからない私だが、男性はそばに居てずっと頭を撫でてくれていた。
「泣くほど美味しかった?」
雑炊を食べ終わる頃、私の目は充血し、パンパンに腫れてしまっていた。
こんな顔では、誰も私を『可愛い、綺麗』などと褒めてはくれないだろう。
現に、目の前の男性は泣き止んだ私の顔を見て「酷い顔」と笑った。
「確認しても良い?」
少し落ち着いてきたところで、初めてはっきりと口を開いた。
男性は私と向き合うように床に胡座をかいて座っている。
私はベッドに腰掛けている状態のため、どうしても男性よりも目線が高くなる。
これは失礼かと、男性の目線に合わせるよう、私も床に正座をする。
「私を助けてくれたのはあなただよね?」
「これが助けるってことになったのかは知らないけど、ここに連れてきたのは俺だね」
「……ありがとう」
感謝を述べるが、正直特に有難いとは思っていなかった。
あのまま体が冷え切った状態で放って置かれれば、私はもしかしたら今頃死んでしまっていたかもしれない。
けれどそれでも良いと思っていた。
母に必要とされないのならば、私は生きている意味がない。
自分の名前も、体も、心も、何も意味を持たない。
「ありがとうって顔じゃないよね」
「え?」
「ちっとも嬉しそうな顔じゃない」
男性は鋭く、私の心を見透かすようだった。
なんだか気まずくなり、私は男性から目を逸らす。
それでも男性は真っ直ぐに私を見つめていた。