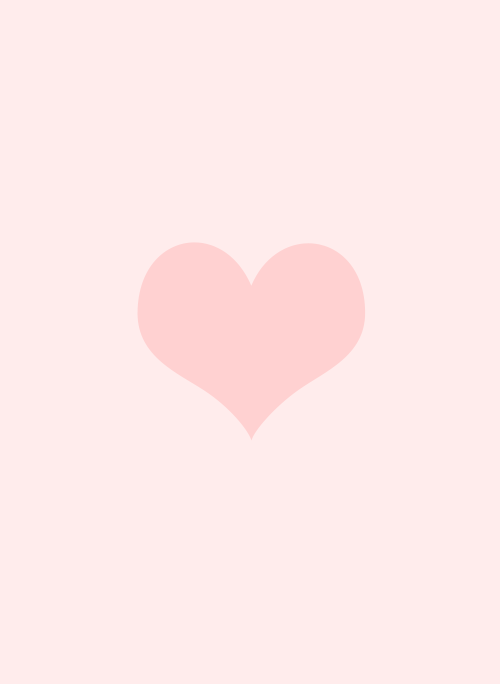「…あ」
ぽたり、と響いた雨音。
人類が滅亡しかけていても変わらず降り注ぐ天の恵み、その音は随分心地がいい。
このまま暫し耳を傾け、うたた寝でもしようかと思い始めた、そんな時だった。
「マァスター?いらっしゃいます?」
「…メフィスト……?」
「あぁ良かった、ここにいなければ改めて探しに行くところでしたよ」
きょろきょろと何かを探すように俺の部屋へ入ってきたメフィストは、ソファに転がる俺の姿をみとめると、いつも通りの胡散臭い笑顔で側へ近寄ってきた。
「何の用だ…遊んで欲しい、とかなら他を当たってくれよ」
「んふふ!いやぁ、朝から雨が降り続いておりますでしょう?」
「ああ、そうだな」
「…わたくし、寒いのですよ、マスター」
さっきまでとはうって変わった甘い微笑みを浮かべて、すり、すり、とまるで猫の様に頬を寄せてくる。
その仕草をかわいいと思ってしまう俺は、やはりどこかおかしいのだろう。
「はぁ…温めてやるから、もっとこっち来い、メフィ」
「おや?随分お優しい事ですねぇ。いつもはもっと抵抗なさるのに」
「…俺も丁度、人肌が恋しかったんだ」
「それはそれは」
余裕ぶった口調を崩してやりたくて、不意を突いてキスをする。
「っ!マス……」
「抵抗すんなよ」
「…ん……」
「そう。いい子だな、メフィ」
そう言って撫でてやれば、子供扱いされたと思ったのか頬をぷくりと膨らませた。
「……わたくし、子供じゃありませんよ?」
「知ってる。子供ならこんなことしない」
ほどよく盛り上がった肉付きのいい胸を揉みしだき、その感触を堪能する。
すると、少しだけ体温が上がり頬が上気してゆくのが分かった。
「あ…っ」
「気持ちいいか?」
「は、い…いい、です、よ……っん!」
薄桃色の、ぷっくりとした乳首を指でつまんで捻りあげれば、メフィストは背を仰け反らせて艶めいた声をあげた。
「はあっ……!ふ、くぅ…っ」
もう片方の手をわき腹へ滑らせ、そのまま下肢の方へとなぞれば、その中心にあるそれは既に反応し始めていた。
「は…ん、マ、スター…そこ、はぁ……!」
「…もうこんなになってる。エッチだな、メフィは」
「あなたの、せいではないですか…っ」
「うん、確かに俺のせいだ」
先走りの蜜がしたたるメフィストのそれを扱き、裏筋を擦り、攻め立てる。
先端をぐりぐりと少し強めになぶってやると、悲鳴にも似た嬌声を上げながら体を痙攣させた。
「ひ…っ、うあ、あぁあっ……も、やめ…っは、あ!」
「やめる?こんなに気持ちよさそうなのに…?」
「あ、あぁ…マス、ター……」
メフィストは蕩けた瞳でこちらを見つめ、肩に腕を回して抱きついてくる。
そして、吐息混じりの甘ったるい声で、懇願するように囁いた。
「…疼くのです、わたくしの腹の中が…お願いですから、焦らさないで」
「メフィスト…」
僅かな沈黙を肯定と受け取ったのか、メフィストは自身の柔らかく開ききった蕾に俺の欲望をあてがう。
指で慣らしていないにも関わらず、そこは貪欲な程に柔軟にそれを飲み込んだ。
「…あ、あ……っ」
「メフィスト…?大丈夫、か……」
「はっ……あまりにも、っん、具合が、宜しいもので…っふ!」