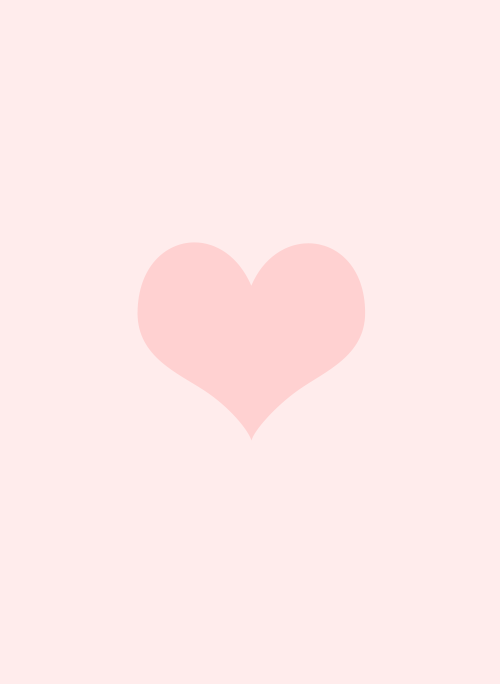「どうしても、行くんだよね」
「うん」
迷いなく頷いた佐島に、小夜は仄かに泣きそうに笑った。
「そう言うと思った」
「…小夜」
ためらいがちに名を呼んだ佐島に、首を振る。
「今、一番傷ついているのはきっと葵だから。お願い、行ってあげて」
「分かった」
出ていく間際に、ありがとう、と口の形を動かして笑った佐島を見つめて、小夜は精一杯の力で笑い返した。
完全に足音がしなくなったのを聞き届けてから、小夜は床にくずおれた。
「…………っ……」
膝を両手で抱えると、必死に嗚咽を抑えようとする。
今辛いのは葵だ。
私じゃない。
葵が苦しんでいるんだ。
言い聞かせて止めようとしても、涙は勝手に出てきて、小夜はそれを腹立たしく思った。
最後まで私のためだった。
器が違う、と呟く。
どうして葵は、私の友人の彼女は、ああまで一生懸命になれるのだろう。
傷つけた私なのに、優しくする価値もないのに、わざわざ悲しい嘘をついてくれてまで。
その決意を返せるだけの自分になりたくて。
だのに、そんなことをされたらますます遠ざかっていくばかりだ。
「会いたいよ…」
今はその優しさが、あの眼差しが、何にも代えがたく恋しかった。
「うん」
迷いなく頷いた佐島に、小夜は仄かに泣きそうに笑った。
「そう言うと思った」
「…小夜」
ためらいがちに名を呼んだ佐島に、首を振る。
「今、一番傷ついているのはきっと葵だから。お願い、行ってあげて」
「分かった」
出ていく間際に、ありがとう、と口の形を動かして笑った佐島を見つめて、小夜は精一杯の力で笑い返した。
完全に足音がしなくなったのを聞き届けてから、小夜は床にくずおれた。
「…………っ……」
膝を両手で抱えると、必死に嗚咽を抑えようとする。
今辛いのは葵だ。
私じゃない。
葵が苦しんでいるんだ。
言い聞かせて止めようとしても、涙は勝手に出てきて、小夜はそれを腹立たしく思った。
最後まで私のためだった。
器が違う、と呟く。
どうして葵は、私の友人の彼女は、ああまで一生懸命になれるのだろう。
傷つけた私なのに、優しくする価値もないのに、わざわざ悲しい嘘をついてくれてまで。
その決意を返せるだけの自分になりたくて。
だのに、そんなことをされたらますます遠ざかっていくばかりだ。
「会いたいよ…」
今はその優しさが、あの眼差しが、何にも代えがたく恋しかった。