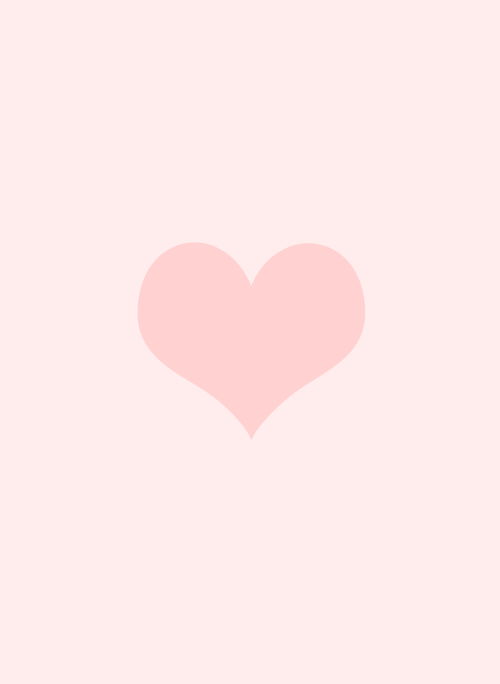「水仙、水仙。こちらへおいで。」
「…琥珀!会いたかった。」
夏麻(リネン)のシャツに身を包んだ少年は“シッ”と人差し指を口元に当てながら、水仙を部屋から連れ出した。向かいのキッチンには檸檬や甜瓜(メロン)、柘榴などが砂糖漬けにされている。アルコホオルや炭酸で割ったら美味しそうだ。
「喉が乾かないかい?」
「もうカラカラ!僕、ジュウスが飲みたい。」
「あんなに全力疾走するから。」
「…見ていたの?」
「窓からね。」
水仙は途端に恥ずかしくなった。
琥珀に、心の内をすべて見透かされたような気持ちになったのだ。
「大人達には、内緒だよ。」
そう言って琥珀が水仙に差し出したのは黄金色に光る曹達(ソオダ)水。浮かぶ氷が石英のようだ。結晶に小さな気泡がいくつも弾けては消えていく。
「これは何の飲み物?」
「太陽の雫さ。」
「たいようのしずく。」
水仙には難しい事は理解らない。しかし琥珀がそう言うのなら“そう”なのだと思った。この幾らか歳上の聡明な少年は自分の知らない事を沢山知っていて、親戚の子供は他にもいたが、水仙にとっては琥珀こそが眩しい太陽そのものであった。
「おいしい。」
初めて喉を過ぎる炭酸水は、淡い酸味を舌に残して腹に落ちた。
「……おいで。」