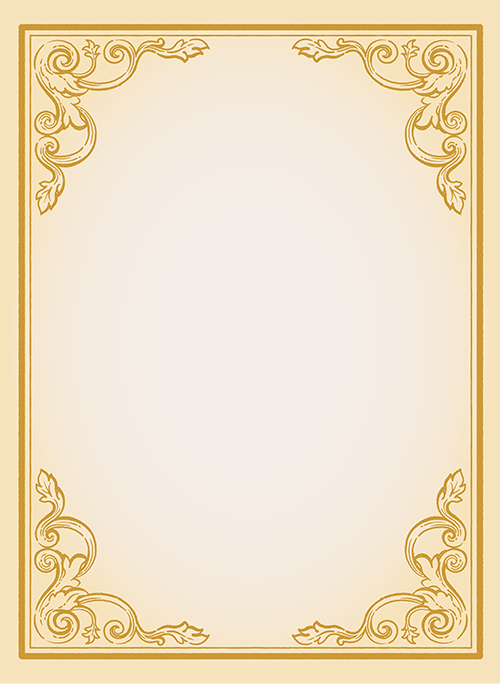「弱味見せる相手、間違えてるよ。見せて良いのは、今スクランブルエッグの練習してる奴。俺じゃないでしょ?」
『え、あっ…。』
キュッ、キュッ、キュ…とグラスを慣れた手付きで拭き上げる音と、ジャズの心地好いリズムに耳を傾けながら手元に残るオレンジジュースに口をつけた。
「…学歴だ何だって気にする親は居るけど…それって子供のステータスを自分のお飾りにしたいだけなんだよね、自慢話のタネっていうのかな。」
相変わらずの冷静な口調で眈々と言葉を並べているけど…その声はどことなく元気が無くて…そんな彼に何も言えずに居た。
「…十人十色、なのにね。子供には子供の幸せがあるのに、勝手だよな……本当。」
『…っ……。』