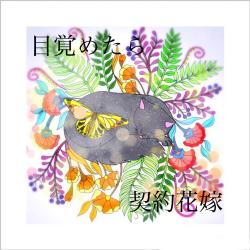「でも…………。」
「ん?」
高城さんの視線を辿れば、私と副社長の手元に向いている。
はっと我に返った。いつもの癖で―――。
「ラブラブなんですね、副社長と松井さん。」
料理を二人で分けて食べていた。
「喧嘩してるかと思ったけど?」
「………してた筈なんだけどね?」
今朝の副社長室でのやり取りがあっても、結局は癖でランチを分けて食べていた。
「朱里だけは特別だ。」
「副社長も言いますね?それって誰にでもですか?」
「高城、伊藤と入れ替えて、賢人の直下にするぞ?社長秘書は更に忙しいからな?」
「副社長、冗談でも笑えないです。」
「朱里が怒るから、冗談でも女の話はするな。」
「松井さんもヤキモチ妬くんだね?」
高城さんの言葉に動きを止めた。
私がヤキモチ?
「気付いてないのは朱里だけだ。」
勝ち誇ったような副社長の声に私は完璧に考え込んだ。
ヤキモチを妬いてる?
「松井さん、女の話で怒るって事はヤキモチでしょ。」
笑う高城さんに頬が染まっていく。
そうなのかな?
知らされた真実にチラリと副社長を見れば、ニヤニヤと私を見下ろしていた。
全員のランチを奢っても上機嫌な副社長に、よっぽど嬉しかったんだと確信した。
「ん?」
高城さんの視線を辿れば、私と副社長の手元に向いている。
はっと我に返った。いつもの癖で―――。
「ラブラブなんですね、副社長と松井さん。」
料理を二人で分けて食べていた。
「喧嘩してるかと思ったけど?」
「………してた筈なんだけどね?」
今朝の副社長室でのやり取りがあっても、結局は癖でランチを分けて食べていた。
「朱里だけは特別だ。」
「副社長も言いますね?それって誰にでもですか?」
「高城、伊藤と入れ替えて、賢人の直下にするぞ?社長秘書は更に忙しいからな?」
「副社長、冗談でも笑えないです。」
「朱里が怒るから、冗談でも女の話はするな。」
「松井さんもヤキモチ妬くんだね?」
高城さんの言葉に動きを止めた。
私がヤキモチ?
「気付いてないのは朱里だけだ。」
勝ち誇ったような副社長の声に私は完璧に考え込んだ。
ヤキモチを妬いてる?
「松井さん、女の話で怒るって事はヤキモチでしょ。」
笑う高城さんに頬が染まっていく。
そうなのかな?
知らされた真実にチラリと副社長を見れば、ニヤニヤと私を見下ろしていた。
全員のランチを奢っても上機嫌な副社長に、よっぽど嬉しかったんだと確信した。