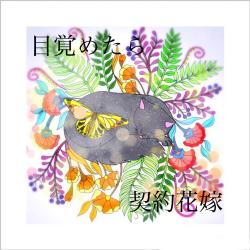「朱里、愛してる。高校の頃から忘れられない女だった。」
「尚輝。」
「俺も初めての同棲は不安だ。朱里と不安なのは同じだ。」
囁く尚輝の声に耳を傾ける。あまりに優しい声に涙が浮かんできそうになる。
「朱里、俺を愛してくれてるか?」
小さな声で囁かれる声に頷く。尚輝が嬉しそうに微笑む顔を見つめる。
「俺も。俺と朱里の気持ちは同じだ。大丈夫、親にも俺から説明するし上手くいく。」
「うん。」
尚輝の手が頬から離れていくのを寂しく思った。思わず、尚輝の手を掴んだ。
「朱里?」
「ごめん、もう少し触れていてくれる?」
「ははっ、ああ。」
温もりが頬へと戻る。不安を打ち消してくれる温もりに擦り寄る。
「尚輝、ありがとう。」
「ああ。週末の予定だけ聞いてくれ。」
「うん。」
「俺に任せておけ。」
「うん。」
今度こそ、私の頬から手が離れていった。見つめ合う目に笑みを浮かべた。
「尚輝。」
「俺も初めての同棲は不安だ。朱里と不安なのは同じだ。」
囁く尚輝の声に耳を傾ける。あまりに優しい声に涙が浮かんできそうになる。
「朱里、俺を愛してくれてるか?」
小さな声で囁かれる声に頷く。尚輝が嬉しそうに微笑む顔を見つめる。
「俺も。俺と朱里の気持ちは同じだ。大丈夫、親にも俺から説明するし上手くいく。」
「うん。」
尚輝の手が頬から離れていくのを寂しく思った。思わず、尚輝の手を掴んだ。
「朱里?」
「ごめん、もう少し触れていてくれる?」
「ははっ、ああ。」
温もりが頬へと戻る。不安を打ち消してくれる温もりに擦り寄る。
「尚輝、ありがとう。」
「ああ。週末の予定だけ聞いてくれ。」
「うん。」
「俺に任せておけ。」
「うん。」
今度こそ、私の頬から手が離れていった。見つめ合う目に笑みを浮かべた。