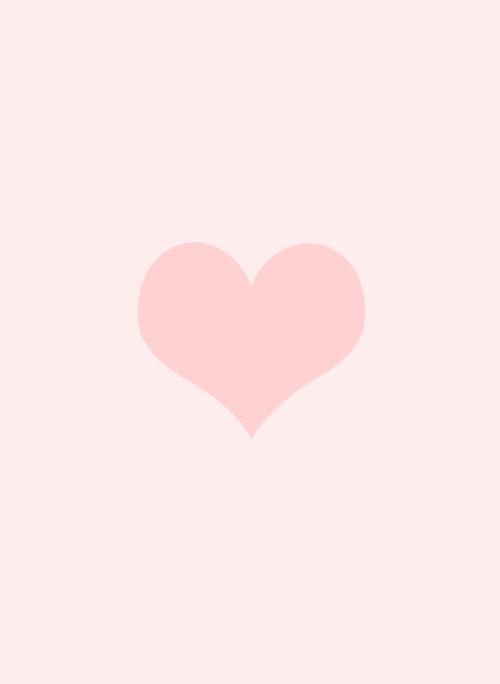月日が経ち、遥は、有森を大輔と名前で呼ぶようになり、有森も遥と呼ぶようになっていた。
遥は、有森と付き合っていて不満はなかった。心を開いて有森に飛び込んだ遥を大切にしてくれている有森だったが、彼は、母親と遥を未だに逢わせてくれないし、余り母親や生い立ちについて話さなかったのだ。
「ね、大輔、明日は、私も病院に行きたいの。」
「…」
「貴方を生んでくれたお母様に会ってみたいの。大輔は、私をお母様に会わせるのが嫌なの?」
「…解った。でも、何言われても気にするなよ。お袋は、病気なんだから。…それに」
「何」
「…いや…とにかく、まともじゃないから、覚悟してよ」
「うん。」
いつも明るい大輔の顔が硬い表情になっていた。
いつもそうなのだ。遥の事は、何でも知っていて受け入れてくれている彼だが、母親の事になると辛そうなのに遥に話してはくれない。
∽∽∽∽∽∽
とうとう遥は、大輔の母に会うのだ。
先に大輔が病室に入って、遥は、少し待たされた。ドキドキ…
「遥入れよ」
「はい」
遥が病室に入ると 大輔の傍に小柄な女性。
大輔の母は、遥が想像していたより若く見え、大輔とよく似ている。
「…こんにちは。」
遥が挨拶をしようと歩み寄るとその女性が遥の手を握った。
「知ってるわ。奥様には、申し訳ありませんが…私は大輔を手放す積もりはありません…帰って下さい。」
「…?あの、いえ、私は…」
「どんな事があっても大輔は渡さない!帰って!帰って!」
激しく怒鳴りながら遥を睨み付ける目…
余りの剣幕にたじろんでいると遥の手を握る手が力強くなる。大輔の母の爪が遥の腕に当たり痛い。 遥が大輔の母の手を見るとハッ と なった。痩せたその腕には、無数の傷痕がまるで模様のようについていた。
大輔が母親の手を遥から離し、宥めすかすが 興奮状態になり 何やらわめき立てた。
「ごめん、遥外に…」
「はい」
…遥は大輔が逢わせたがらない訳をすでに納得しながら病室の外で驚きでドキドキしている自分を落ち着かせていた。
大輔が呼んだのだろう。看護師とドクターらしき人が慌ただしく母の病室に入って行った。
遥は、有森と付き合っていて不満はなかった。心を開いて有森に飛び込んだ遥を大切にしてくれている有森だったが、彼は、母親と遥を未だに逢わせてくれないし、余り母親や生い立ちについて話さなかったのだ。
「ね、大輔、明日は、私も病院に行きたいの。」
「…」
「貴方を生んでくれたお母様に会ってみたいの。大輔は、私をお母様に会わせるのが嫌なの?」
「…解った。でも、何言われても気にするなよ。お袋は、病気なんだから。…それに」
「何」
「…いや…とにかく、まともじゃないから、覚悟してよ」
「うん。」
いつも明るい大輔の顔が硬い表情になっていた。
いつもそうなのだ。遥の事は、何でも知っていて受け入れてくれている彼だが、母親の事になると辛そうなのに遥に話してはくれない。
∽∽∽∽∽∽
とうとう遥は、大輔の母に会うのだ。
先に大輔が病室に入って、遥は、少し待たされた。ドキドキ…
「遥入れよ」
「はい」
遥が病室に入ると 大輔の傍に小柄な女性。
大輔の母は、遥が想像していたより若く見え、大輔とよく似ている。
「…こんにちは。」
遥が挨拶をしようと歩み寄るとその女性が遥の手を握った。
「知ってるわ。奥様には、申し訳ありませんが…私は大輔を手放す積もりはありません…帰って下さい。」
「…?あの、いえ、私は…」
「どんな事があっても大輔は渡さない!帰って!帰って!」
激しく怒鳴りながら遥を睨み付ける目…
余りの剣幕にたじろんでいると遥の手を握る手が力強くなる。大輔の母の爪が遥の腕に当たり痛い。 遥が大輔の母の手を見るとハッ と なった。痩せたその腕には、無数の傷痕がまるで模様のようについていた。
大輔が母親の手を遥から離し、宥めすかすが 興奮状態になり 何やらわめき立てた。
「ごめん、遥外に…」
「はい」
…遥は大輔が逢わせたがらない訳をすでに納得しながら病室の外で驚きでドキドキしている自分を落ち着かせていた。
大輔が呼んだのだろう。看護師とドクターらしき人が慌ただしく母の病室に入って行った。