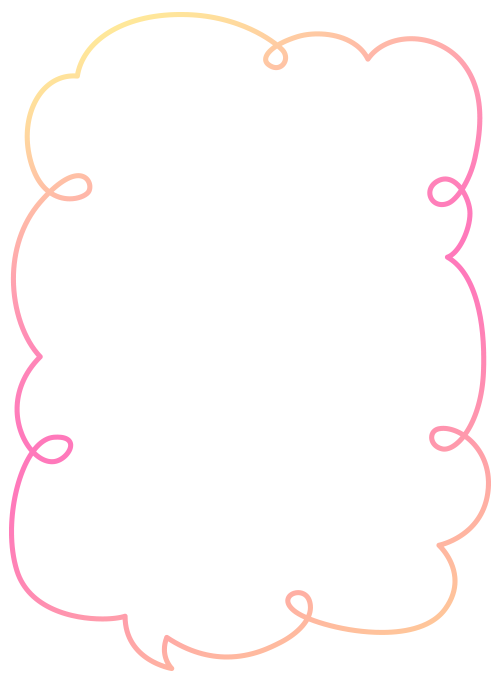「あ、そうだ! ねぇ、手出して」
数分が経ち、最初の会話以来無言だった彼が、唐突に言ってきた。私は驚いて、「えっ?」と聞き返してしまう。その声が思ったより響いて、少し恥ずかしい。
彼を見ると、何故か楽しそうで断りにくかった。
「……こうでいいの?」
恐る恐るながら、私は彼の前へ手を差し出した。
コロン。
何かが手に乗ったようだ。見てみると、飴のようなものが置いてある。
なんだろう、これ。
意図が読めなくて、彼の顔を見上げた。
「それあげる。美味しいよ!」
無邪気に笑って彼は言った。なんで私に?とは思ったが、曖昧に笑って受け取る。飴は私の大好物だ。いろいろと謎ではあるものの、嬉しいと思った。袋を開け、中の丸いものを口に入れると、不思議な味がした。甘いような、酸っぱいような、それでいて少し苦いような。それなのにそれらが上手く混ざりあっていて、一言で言えば、とても美味しい。
「あめは嫌い?」
飴を口に入れてぼーっとしている私に、彼が聞いてきた。一瞬、飴か雨か分からなかったが、イントネーション的に雨だと判断した。
「あんまり好きじゃないかな」
そう言って笑ってみせると、彼は悪戯っぽく微笑んで言った。
「じゃあ、あめは?」
今度のあめは飴の事だろう。
「そっちは大好物だよー。あなたはどう?」
私の方からも聞いてみた。彼のことが気になり始めたのだ。
別に彼に好意を持ったとかではない。
決してない。強いていえば好奇心。
「俺も好きだよ」
彼が少し声を低くして言ったその言葉に、不覚にもキュンとしてしまった。好意なんてなくったって、まっすぐに見つめてそんなことを言われたら、そうなるのは必然だろう。……なんて、私の惚れっぽさを正当化しようとしているだけなのかもしれない。
改めて彼の顔をよく見ると、相当なイケメンだった。華やかな格好良さというよりは穏やかな感じで、私の好きなタイプの顔である。 そう思うと急に、この状況が恥ずかしくなってきた。自分ながらに現金だと思う。でも、頬が熱くなるのを抑えることは出来なかった。
「あめ」
「ん?」
気がつくと彼は道路の方を見ていた。つられ
て私もそっちを見る。
「雨、止んだね」
確かにもう雨は降っていなかった。空も晴れ始めたようだ。
「もう、帰る?」
私は彼に尋ねた。思ったよりも暗い声が出て、まるで引き留めようとしているかのように聞こえただろう。実際、そういう気持ちが全くなかったとは言えない。
「……まだ、帰らない」
彼はちょっと考える素振りをし、そう答えた。私の気持ちが伝わってしまったのだろうか。もしその上で帰らないと言ったのなら、もっと一緒にいたいと思われていると解釈してもいいのか。
「俺はもうちょっと君と話してみたいなぁ」
彼はそう言葉を続けた。心なしか彼の顔は赤い気がする。表情もさっきより緊張しているように見える。
「私もあなたと話したい」
そんな彼の姿が可愛くて、 気づけば私も素直にそう言っていた。
数分が経ち、最初の会話以来無言だった彼が、唐突に言ってきた。私は驚いて、「えっ?」と聞き返してしまう。その声が思ったより響いて、少し恥ずかしい。
彼を見ると、何故か楽しそうで断りにくかった。
「……こうでいいの?」
恐る恐るながら、私は彼の前へ手を差し出した。
コロン。
何かが手に乗ったようだ。見てみると、飴のようなものが置いてある。
なんだろう、これ。
意図が読めなくて、彼の顔を見上げた。
「それあげる。美味しいよ!」
無邪気に笑って彼は言った。なんで私に?とは思ったが、曖昧に笑って受け取る。飴は私の大好物だ。いろいろと謎ではあるものの、嬉しいと思った。袋を開け、中の丸いものを口に入れると、不思議な味がした。甘いような、酸っぱいような、それでいて少し苦いような。それなのにそれらが上手く混ざりあっていて、一言で言えば、とても美味しい。
「あめは嫌い?」
飴を口に入れてぼーっとしている私に、彼が聞いてきた。一瞬、飴か雨か分からなかったが、イントネーション的に雨だと判断した。
「あんまり好きじゃないかな」
そう言って笑ってみせると、彼は悪戯っぽく微笑んで言った。
「じゃあ、あめは?」
今度のあめは飴の事だろう。
「そっちは大好物だよー。あなたはどう?」
私の方からも聞いてみた。彼のことが気になり始めたのだ。
別に彼に好意を持ったとかではない。
決してない。強いていえば好奇心。
「俺も好きだよ」
彼が少し声を低くして言ったその言葉に、不覚にもキュンとしてしまった。好意なんてなくったって、まっすぐに見つめてそんなことを言われたら、そうなるのは必然だろう。……なんて、私の惚れっぽさを正当化しようとしているだけなのかもしれない。
改めて彼の顔をよく見ると、相当なイケメンだった。華やかな格好良さというよりは穏やかな感じで、私の好きなタイプの顔である。 そう思うと急に、この状況が恥ずかしくなってきた。自分ながらに現金だと思う。でも、頬が熱くなるのを抑えることは出来なかった。
「あめ」
「ん?」
気がつくと彼は道路の方を見ていた。つられ
て私もそっちを見る。
「雨、止んだね」
確かにもう雨は降っていなかった。空も晴れ始めたようだ。
「もう、帰る?」
私は彼に尋ねた。思ったよりも暗い声が出て、まるで引き留めようとしているかのように聞こえただろう。実際、そういう気持ちが全くなかったとは言えない。
「……まだ、帰らない」
彼はちょっと考える素振りをし、そう答えた。私の気持ちが伝わってしまったのだろうか。もしその上で帰らないと言ったのなら、もっと一緒にいたいと思われていると解釈してもいいのか。
「俺はもうちょっと君と話してみたいなぁ」
彼はそう言葉を続けた。心なしか彼の顔は赤い気がする。表情もさっきより緊張しているように見える。
「私もあなたと話したい」
そんな彼の姿が可愛くて、 気づけば私も素直にそう言っていた。