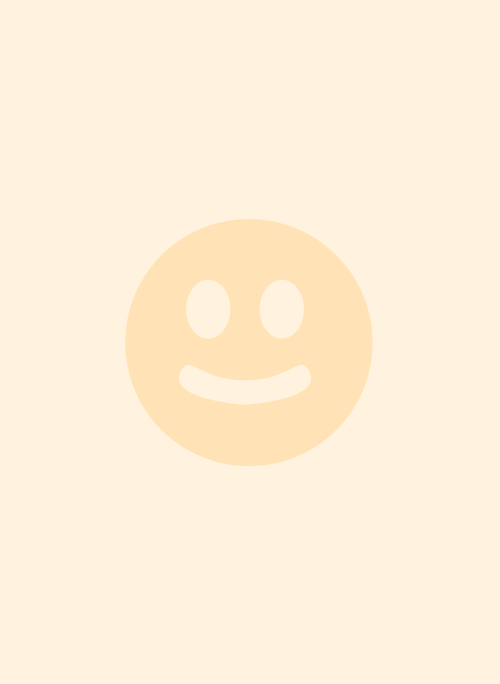「ごめん大くん!」
「いいよ。乗って」
大貴はわたしの腕を掴んだ。
「キャッ!!」
まだ急なボディータッチには慣れていない。
わたしは一歩後退り、悲鳴を上げた。
「ご、ごめん」
「まだ慣れないかぁ」
大貴がため息を吐いたとき
「行くなよ!!」
と、腕を掴まれた。
「ろ、狼くん…!?」
狼くんは何も言わずにわたしを塾の裏に連れていき
壁に押しつけた。
「ちょ……狼…………んっ」
荒々しく奪われた唇からは
狼くんの熱が伝わってきた。
「ん…ぅあ…あ……」
狼くんはわたしの唇を解放し
首筋に自らの唇を這わせた。
「あ…あ……や、…ァ――」
抵抗しても、無駄だ。
また…過去の記憶が蘇りつつあった。
「い、や……イヤアァァァ――」
闇をも裂くようなわたしの悲鳴に、狼くんは唇を放した。
「怖い…!!怖いの!!
お、男の人が…ァ…怖い――」
「!!」
わたしは頭を抱え、その場にしゃがみ込んだ。
「っ!………ごめん…」
狼くんは小さく呟き
去っていった。