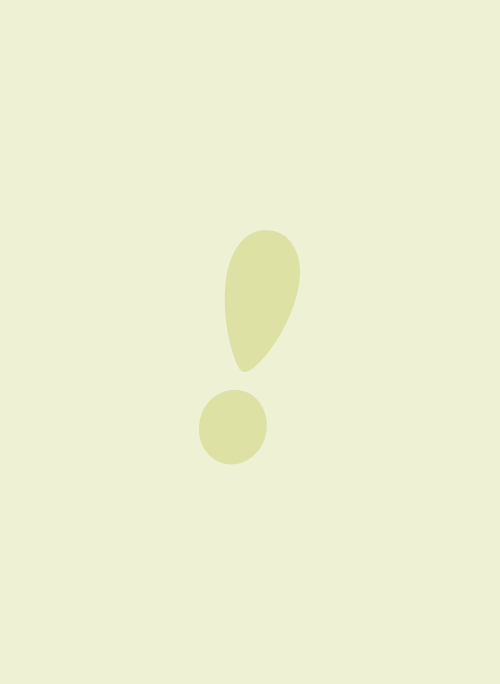「だけど、1回しか言ってくれないなんてやだ…。」
「…えっ?」
予想外の言葉に、俺は耳を疑った。
「もっと沢山言って。これっきりなんてやだよ…。」
思いもしなかった彼女のわがまま。
泣きながら笑う彼女の表情を見て、俺も自然と笑顔になった。
「何回も言ったら、有りがたみがないだろう?」
「毎日言ってよ。」
「…無理。」
彼女はまだ少しだけ目に涙を浮かべて笑うと、姿勢を変えて俺の腰に両腕を回した。
そして俺の胸に頬をすり寄せると、彼女は言った。
「さっきの言葉、プロポーズみたいだった。」
「あぁ…。」
思い返すのも恥ずかしいけれど、俺はそういう事を言った。
「そう思ってくれてもいいよ。」
「そうなんだ。」
“フフフッ”と微笑んで、彼女は目を閉じた。
「だけど…。」
俺の言葉が続いた事で、彼女は俺の顔を見上げた。
俺を見つめる彼女の瞳が揺れている。
「だけどその時が来たら、もう一度ちゃんと言うよ。」
そう言って、微笑みながら頭を撫でると、
「せんせぇ…。」
彼女の顔が、また涙と共にクシャッと歪み、
俺はそんな彼女を抱き寄せて、何度も頭を撫で続けた。
「だからその時が来るまで、ちゃんと覚えててくれよ…?」
俺は彼女の顎を軽く持ち上げてキスをした。
約束のキスだ。
震える彼女の唇は温かくて、
やっぱり涙の味だった。
そして、
“愛おしい”
この気持ちが俺の全てだと、
そう、感じていた―…
「…えっ?」
予想外の言葉に、俺は耳を疑った。
「もっと沢山言って。これっきりなんてやだよ…。」
思いもしなかった彼女のわがまま。
泣きながら笑う彼女の表情を見て、俺も自然と笑顔になった。
「何回も言ったら、有りがたみがないだろう?」
「毎日言ってよ。」
「…無理。」
彼女はまだ少しだけ目に涙を浮かべて笑うと、姿勢を変えて俺の腰に両腕を回した。
そして俺の胸に頬をすり寄せると、彼女は言った。
「さっきの言葉、プロポーズみたいだった。」
「あぁ…。」
思い返すのも恥ずかしいけれど、俺はそういう事を言った。
「そう思ってくれてもいいよ。」
「そうなんだ。」
“フフフッ”と微笑んで、彼女は目を閉じた。
「だけど…。」
俺の言葉が続いた事で、彼女は俺の顔を見上げた。
俺を見つめる彼女の瞳が揺れている。
「だけどその時が来たら、もう一度ちゃんと言うよ。」
そう言って、微笑みながら頭を撫でると、
「せんせぇ…。」
彼女の顔が、また涙と共にクシャッと歪み、
俺はそんな彼女を抱き寄せて、何度も頭を撫で続けた。
「だからその時が来るまで、ちゃんと覚えててくれよ…?」
俺は彼女の顎を軽く持ち上げてキスをした。
約束のキスだ。
震える彼女の唇は温かくて、
やっぱり涙の味だった。
そして、
“愛おしい”
この気持ちが俺の全てだと、
そう、感じていた―…