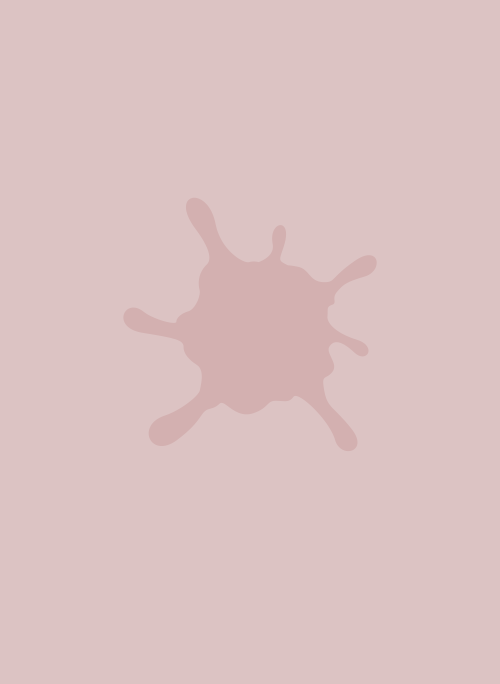◆
次の日はさすがに気が咎めて、おとなしく学校へ行った。相変わらず私は一人だったけれど、もうあの写真を見てほっとする癖はいずこへか姿をくらましていた。どうして、なのだろう。篤がいるから? それとも、本物に会えたからもう、写真は要らないというのだろうか。
清掃委員の仕事を終えた放課後、私は鞄を取りに閉じきられた教室のドアに手をかけた。何やら声がする。男と女の声だ。
「だからさあ、あの子は無理だよ。もう構うのやめなって!」
これは、絵梨香の声だ、とすぐに分かった。
少しきつい調子の、高すぎるような、女特有の声。
まさか、告白? それにしては随分騒がしい声音だ。思わず入るのを躊躇う。
「確かに篤にとっては幼馴染かもしれないけど、今は私がいるじゃん!」
え......。私の脳は一瞬停止して、すぐに正答を導き出そうとして、また停止した。
「そんなにあの子が大事なの!? 私より?」
「いや......」
「言ったじゃん、あの子は幽霊屋敷に通う変な子なの! 二次元に本気で恋してるちょっと気持ち悪い子なの! わかっているでしょう!?」
「わかってるけどさ」
「それに、私の方が篤君のこと、大事に大切に思ってるってことだって、わかってるでしょ......?」
「絵梨香......」
教室から漏れ出す沈黙。無音が霧散して廊下にも伝わる。それが何を意味しているか、分からない私でもなかった。何だろう。頭がくらくらする。私の足は自然踵を返していた。そのとき。
「あっ」
二人がカップルにふさわしからぬ鋭い声を出した。カーテンを閉めようとしたその隙に、それは瞳に映し出されたらしかった。
「何あれ。煙......」
「あれは......お婆ちゃんの店の方だっ」
え......。
私は我ながら荒い足取りで、気が付けば屋敷の方角に走っていた。
「君人さまっ」
「暁月っお前っ」
教室のドアを急いて開けたのはやはり篤だった。けれど彼にかまってはいられない。
君人さまは、動けないんだ。あそこで私に話しかけ、微笑むくらいしか出来ない。道路を走り抜け、立ち昇る黒煙の根本を眼で探す。ああ、やはり幽霊屋敷だ! そこにたどり着く途中、消防とすれ違った。今は帰宅時で道が混んでいて、車がどけても私の足の方が速い。
「うわあ、本当に火事だよ」
「これ中にいる人ダメなんじゃないか」
幽霊屋敷の少し離れたところより、みなが携帯をかざして撮影している。屋敷を食い荒らし、燃え盛る火事の様子を。
「君人さまっ」
私は思わずそう声を発して、気が付いたら炎に飲まれる屋敷の中に飛び込んでいた。瞬時のことで、行く手を阻む人の手もなかった。
足の裏が熱い。屋敷が燃え盛っている。けれど私の胸には安堵が広がっていた。燃え盛る柱と、炎から逃れて着いた地下はまだ熱が届いていなかった。まるで神域のように、冷え切って静謐な時間がそこにあった。
「君人さま......」
私がそう声をかけて、変わらず美しい人形に近づく。
「一緒に、逃げましょう」
そう続けようとした、その時だった。私の身体は恐怖に肌泡立った。突如、強い力で私の腕を掴んだものがある。それは人形の手だった。白くて、強い力を持つ、手。
「君、人、さま......?」
まるでここにいて一緒に焼け焦げようね、と言うように、その腕は私を離さなかった。
ドンと背後から音がして、天井の一部が焼け焦げて落ちた。鼻に熱の匂いがせまる。
「君人さま......いやっいやああああっ」
私は次には恐怖に叫びまわっていた。恐ろしかった。死が目の前に降り立つと、喉が切り裂かれたように緊迫した。眩暈がとまらない。人形は手を離してくれない。声が声にならない。わめきちらしてのたうっていた先で、消防の人の強い手が私を救った。そこで意識が途切れた。
◆
消防隊員に助けられ怒鳴られて、解放されたのちに、私はしずしず現れた篤に話を聞いた。
あの人形は、篤のいとこだった。受付のお婆ちゃんの自慢の孫息子を生き写したものだった。そのお孫さんは事故で死んでいたということ。お婆ちゃんはそのショックか痴ほうが進んでいたことを、知った。
「お婆ちゃんは毎日あの人形に話しかけてたんだ」
もうそれも、出来なくなったけど。
お婆ちゃんは逃げ遅れて命は助かったが、喉が焼け切れて声が出なくなったということも、その時知れた。
「あの人形を遠くにやると、お婆ちゃんは泣きわめいて首を切って自殺未遂を起こした。近くに置いておくと気も休まるらしかった。だから、あれを地下室に閉じ込めた。あれは人の精神を壊して喰らう、呪われた人形のような気がしたから。それに」
人形は話しかけると、魂を持つというから。
そう、だったのか――、私はふいに眼がしらが熱くなって、その場にしゃがみ込んだ。何が悲しかったのかは、分からない。
◆
次の日、一人でお婆ちゃんの見舞いに行き、帰宅して無人の自室に戻ったとき、私はふいに声を漏らした。
「君人......さま......」
薄闇の延べられたベッドの上には君人さまの生首があった。自分で来たのか、それとも持ってきたのか、それさえも分からない。ただわかっていることは、君人さまは魔族の末で、人を本当は喰らいたがっているということだった。
「人形は話しかけると魂を持つからね」
ふと、そんな声がよぎった。抱き上げた君人さまの生首。その口元に、牙が覗いた気がした。
了
次の日はさすがに気が咎めて、おとなしく学校へ行った。相変わらず私は一人だったけれど、もうあの写真を見てほっとする癖はいずこへか姿をくらましていた。どうして、なのだろう。篤がいるから? それとも、本物に会えたからもう、写真は要らないというのだろうか。
清掃委員の仕事を終えた放課後、私は鞄を取りに閉じきられた教室のドアに手をかけた。何やら声がする。男と女の声だ。
「だからさあ、あの子は無理だよ。もう構うのやめなって!」
これは、絵梨香の声だ、とすぐに分かった。
少しきつい調子の、高すぎるような、女特有の声。
まさか、告白? それにしては随分騒がしい声音だ。思わず入るのを躊躇う。
「確かに篤にとっては幼馴染かもしれないけど、今は私がいるじゃん!」
え......。私の脳は一瞬停止して、すぐに正答を導き出そうとして、また停止した。
「そんなにあの子が大事なの!? 私より?」
「いや......」
「言ったじゃん、あの子は幽霊屋敷に通う変な子なの! 二次元に本気で恋してるちょっと気持ち悪い子なの! わかっているでしょう!?」
「わかってるけどさ」
「それに、私の方が篤君のこと、大事に大切に思ってるってことだって、わかってるでしょ......?」
「絵梨香......」
教室から漏れ出す沈黙。無音が霧散して廊下にも伝わる。それが何を意味しているか、分からない私でもなかった。何だろう。頭がくらくらする。私の足は自然踵を返していた。そのとき。
「あっ」
二人がカップルにふさわしからぬ鋭い声を出した。カーテンを閉めようとしたその隙に、それは瞳に映し出されたらしかった。
「何あれ。煙......」
「あれは......お婆ちゃんの店の方だっ」
え......。
私は我ながら荒い足取りで、気が付けば屋敷の方角に走っていた。
「君人さまっ」
「暁月っお前っ」
教室のドアを急いて開けたのはやはり篤だった。けれど彼にかまってはいられない。
君人さまは、動けないんだ。あそこで私に話しかけ、微笑むくらいしか出来ない。道路を走り抜け、立ち昇る黒煙の根本を眼で探す。ああ、やはり幽霊屋敷だ! そこにたどり着く途中、消防とすれ違った。今は帰宅時で道が混んでいて、車がどけても私の足の方が速い。
「うわあ、本当に火事だよ」
「これ中にいる人ダメなんじゃないか」
幽霊屋敷の少し離れたところより、みなが携帯をかざして撮影している。屋敷を食い荒らし、燃え盛る火事の様子を。
「君人さまっ」
私は思わずそう声を発して、気が付いたら炎に飲まれる屋敷の中に飛び込んでいた。瞬時のことで、行く手を阻む人の手もなかった。
足の裏が熱い。屋敷が燃え盛っている。けれど私の胸には安堵が広がっていた。燃え盛る柱と、炎から逃れて着いた地下はまだ熱が届いていなかった。まるで神域のように、冷え切って静謐な時間がそこにあった。
「君人さま......」
私がそう声をかけて、変わらず美しい人形に近づく。
「一緒に、逃げましょう」
そう続けようとした、その時だった。私の身体は恐怖に肌泡立った。突如、強い力で私の腕を掴んだものがある。それは人形の手だった。白くて、強い力を持つ、手。
「君、人、さま......?」
まるでここにいて一緒に焼け焦げようね、と言うように、その腕は私を離さなかった。
ドンと背後から音がして、天井の一部が焼け焦げて落ちた。鼻に熱の匂いがせまる。
「君人さま......いやっいやああああっ」
私は次には恐怖に叫びまわっていた。恐ろしかった。死が目の前に降り立つと、喉が切り裂かれたように緊迫した。眩暈がとまらない。人形は手を離してくれない。声が声にならない。わめきちらしてのたうっていた先で、消防の人の強い手が私を救った。そこで意識が途切れた。
◆
消防隊員に助けられ怒鳴られて、解放されたのちに、私はしずしず現れた篤に話を聞いた。
あの人形は、篤のいとこだった。受付のお婆ちゃんの自慢の孫息子を生き写したものだった。そのお孫さんは事故で死んでいたということ。お婆ちゃんはそのショックか痴ほうが進んでいたことを、知った。
「お婆ちゃんは毎日あの人形に話しかけてたんだ」
もうそれも、出来なくなったけど。
お婆ちゃんは逃げ遅れて命は助かったが、喉が焼け切れて声が出なくなったということも、その時知れた。
「あの人形を遠くにやると、お婆ちゃんは泣きわめいて首を切って自殺未遂を起こした。近くに置いておくと気も休まるらしかった。だから、あれを地下室に閉じ込めた。あれは人の精神を壊して喰らう、呪われた人形のような気がしたから。それに」
人形は話しかけると、魂を持つというから。
そう、だったのか――、私はふいに眼がしらが熱くなって、その場にしゃがみ込んだ。何が悲しかったのかは、分からない。
◆
次の日、一人でお婆ちゃんの見舞いに行き、帰宅して無人の自室に戻ったとき、私はふいに声を漏らした。
「君人......さま......」
薄闇の延べられたベッドの上には君人さまの生首があった。自分で来たのか、それとも持ってきたのか、それさえも分からない。ただわかっていることは、君人さまは魔族の末で、人を本当は喰らいたがっているということだった。
「人形は話しかけると魂を持つからね」
ふと、そんな声がよぎった。抱き上げた君人さまの生首。その口元に、牙が覗いた気がした。
了