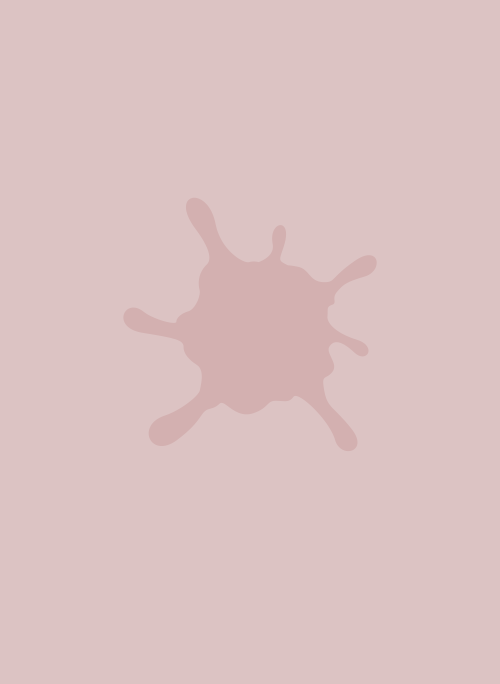私は私と君人様を結ぶ扉が壊されるのを、恐れているのではなかったか?
◆
「ということがあったの、君人さま」
私はあれ以来、ちょくちょく、といっても二週間に一度くらいのペースで、あの人形館に通っていた。目の前にいるのは白皙の美青年。君人さま。無論、他には誰もいない。
「私、見かけ以上に大変な身の上なの。でも、大丈夫。だって私にはもう、君人さまがいるもんね」
ふと、私たち以外何も映らないはずの鏡を見やる。君人さまの背後で私たちを映す、白壁にはめこまれた鏡。それは確かに私のことも映していた。かつて没頭していた水泳のおかげで、仄かに脱色された髪。人形みたいと言われた白い静かな顔。どこといって難はないらしいが、表情の乏しい顔だ、とも言われたものだ。
「もっと笑いなさいよ、って、あの人たちによく言われたんだ。でも、無理だよ。あの家で声高く笑うなんて。そう思うでしょ。君人さまも、ね?」
君人さまは音もたてずに微笑んだ。気がした。気のせいか、とも思う。
軽いめまいがしている。今日、昼に何も食べなかったせいだろうか。気分が少し悪い。
「――もう五時半だ。そろそろ帰るね。君人さま」
その時だった。君人さまがかすかに、瞬きしたように見えた。まるでいかないで、というように。
「う、そ......」
私のこころは歓喜と驚きと、仄かな恐怖を一瞬で巡り巡った。している、ほら、今もした。君人さまが瞬きをした。
「君人さま、生きているの......?」
「んな訳ないだろうが」
そこで、私の意識は突然に現実に引き戻された。この声、間違いない。篤の声だ。
でも、どこから?
ふいに、振り返った先の扉が開いて、現れたのは篤だった。
「何やってんだ、お前」
私は思わず顔を赤らめて、首を振った。
「ううん、何もしてない」
「嘘つけ、上までまる聞こえなんだよ。お前が人形に話しかけてるの」
「うそ......」
「古い建物だからな」
篤は嘆息しているみたいだった。私は恥ずかしくて顔もあげられない。
篤にほれ、と手を引かれて、私は再び屋敷のそとに出た。その後で篤が言った。
「あの受付のお婆ちゃんな、俺の親戚なんだよ。前から言ってたんだ。お前と同じ制服の子がうろちょろしてるって。さすがに、声までは聞き取れなったらしいけどな」
「うそ......」
「ここのオーナーなんだよ。だから婆ちゃんの様子も見がてら気になって来てみたんだ」
婆ちゃんが、気になって? ああ、もう御年だから、か、とは自然に合点した。
「うろつくのは人形みたいに綺麗な子だとも言っていたから、お前かと思って」
そしたら声が聞こえるじゃねえか。そうまで言って、篤は顔を背けた。私はまた赤面した。
「お前、もうここに寄り付かない方がいいよ」
「え......」
「学校でも噂になってんだよ。お前があの幽霊屋敷に通ってるって」
思わず絶句してしまった。誰から聞いたの?とは言えなかった。たぶん、あの私を気味悪がり、嫌うクラスの誰かだと思ったから。押し黙る私を一瞥し、篤がまた顔を背けた。
「とにかく、もう、あの人形に話しかけるのやめろよな。俺がかわりに聞いてやるから」
あっと、今度は篤が顔を赤らめたのがわかった。私の胸に、緊迫感が広がっていく。まずい。やめて、やめて。嬉しいより先に、絵梨香の顔と危機感がやってきて、私を苛む。それを見抜いたかのように。
「あ、違うって、そういう意味じゃなくて、クラスメートとしての親切だからな!?」
篤の顔が上気していくのを、私はよほど厭そうな顔で見つめていたに違いない。今度は篤が言葉を失してしまった。それへ私が。
◆
「ということがあったの、君人さま」
私はあれ以来、ちょくちょく、といっても二週間に一度くらいのペースで、あの人形館に通っていた。目の前にいるのは白皙の美青年。君人さま。無論、他には誰もいない。
「私、見かけ以上に大変な身の上なの。でも、大丈夫。だって私にはもう、君人さまがいるもんね」
ふと、私たち以外何も映らないはずの鏡を見やる。君人さまの背後で私たちを映す、白壁にはめこまれた鏡。それは確かに私のことも映していた。かつて没頭していた水泳のおかげで、仄かに脱色された髪。人形みたいと言われた白い静かな顔。どこといって難はないらしいが、表情の乏しい顔だ、とも言われたものだ。
「もっと笑いなさいよ、って、あの人たちによく言われたんだ。でも、無理だよ。あの家で声高く笑うなんて。そう思うでしょ。君人さまも、ね?」
君人さまは音もたてずに微笑んだ。気がした。気のせいか、とも思う。
軽いめまいがしている。今日、昼に何も食べなかったせいだろうか。気分が少し悪い。
「――もう五時半だ。そろそろ帰るね。君人さま」
その時だった。君人さまがかすかに、瞬きしたように見えた。まるでいかないで、というように。
「う、そ......」
私のこころは歓喜と驚きと、仄かな恐怖を一瞬で巡り巡った。している、ほら、今もした。君人さまが瞬きをした。
「君人さま、生きているの......?」
「んな訳ないだろうが」
そこで、私の意識は突然に現実に引き戻された。この声、間違いない。篤の声だ。
でも、どこから?
ふいに、振り返った先の扉が開いて、現れたのは篤だった。
「何やってんだ、お前」
私は思わず顔を赤らめて、首を振った。
「ううん、何もしてない」
「嘘つけ、上までまる聞こえなんだよ。お前が人形に話しかけてるの」
「うそ......」
「古い建物だからな」
篤は嘆息しているみたいだった。私は恥ずかしくて顔もあげられない。
篤にほれ、と手を引かれて、私は再び屋敷のそとに出た。その後で篤が言った。
「あの受付のお婆ちゃんな、俺の親戚なんだよ。前から言ってたんだ。お前と同じ制服の子がうろちょろしてるって。さすがに、声までは聞き取れなったらしいけどな」
「うそ......」
「ここのオーナーなんだよ。だから婆ちゃんの様子も見がてら気になって来てみたんだ」
婆ちゃんが、気になって? ああ、もう御年だから、か、とは自然に合点した。
「うろつくのは人形みたいに綺麗な子だとも言っていたから、お前かと思って」
そしたら声が聞こえるじゃねえか。そうまで言って、篤は顔を背けた。私はまた赤面した。
「お前、もうここに寄り付かない方がいいよ」
「え......」
「学校でも噂になってんだよ。お前があの幽霊屋敷に通ってるって」
思わず絶句してしまった。誰から聞いたの?とは言えなかった。たぶん、あの私を気味悪がり、嫌うクラスの誰かだと思ったから。押し黙る私を一瞥し、篤がまた顔を背けた。
「とにかく、もう、あの人形に話しかけるのやめろよな。俺がかわりに聞いてやるから」
あっと、今度は篤が顔を赤らめたのがわかった。私の胸に、緊迫感が広がっていく。まずい。やめて、やめて。嬉しいより先に、絵梨香の顔と危機感がやってきて、私を苛む。それを見抜いたかのように。
「あ、違うって、そういう意味じゃなくて、クラスメートとしての親切だからな!?」
篤の顔が上気していくのを、私はよほど厭そうな顔で見つめていたに違いない。今度は篤が言葉を失してしまった。それへ私が。