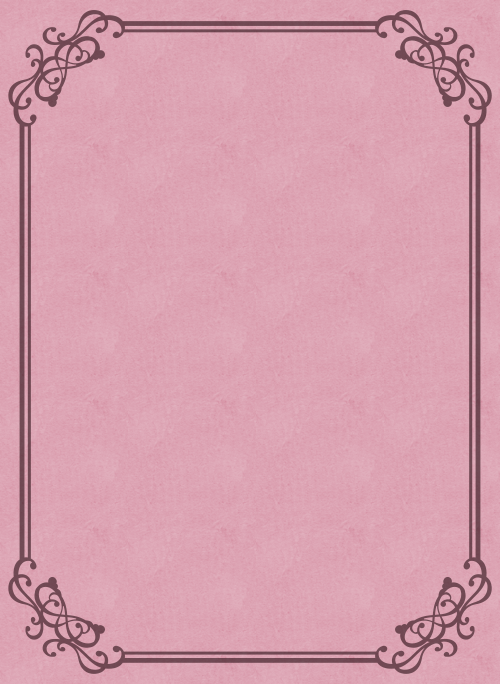「おつかれさま、美鶴」
その声に振り返ると、透がいる。今朝見かけた“透によく似た医師”は本人だったのか。
「……透さん、ですか?」
「夫の顔を忘れたのか?」といいながら透は美鶴の隣に座った。間近でみても紛れもなく自分の夫だ。だが理解が追い付いていかない。
「どうしてここに? それより、その格好……」
濃紺のスクラブに白衣を羽織った姿は透の精悍な顔つきを引き立てていて見とれてしまいそうになる。スーツ姿ももちろんだが白衣姿はそれ以上に素敵だ。今朝看護師たちが騒いでいたのも納得だ。
「俺は医者なんだから白衣を着ていてもおかしくはないだろう?」
「それはそう、ですけど……でも、どうしてこの病院に?」
「この病院の運営は四季グループがしている。部門の統括しているのは俺なんだ。現場の状況を把握するのも経営者として必要なことだからな」
美鶴は軽いめまいを覚えた。将来の自立のために選んだ職場のはずが透の息がかかった病院だったとは。
あっさりと採用されたのも透の力が働いていたのだろうか。
確かめたかったけれど、知ってしまった後が気まずい。知らないほうがいいこともあるのかもしれない――そう美鶴は思い直した。
「驚かせて悪かったな。今後は週に二日程度は現場に出ようと思ってるんだ。救急車の受け例台数を増やさなければいけないからな」
「二日もですか?」
ただでさえ会社の仕事が忙しいというのに現場に出て仕事をする余裕などどこにあるというのか。これ以上多忙を極めればいつか倒れてしまうかもしれない。美鶴は一抹の不安を覚える。
「二日じゃ足りないくらいだけどな。ところで、あなたが仲村先生ですか?」
透は仲村に視線を移した。その目が全然笑っていないことに美鶴の胸はざわめく。