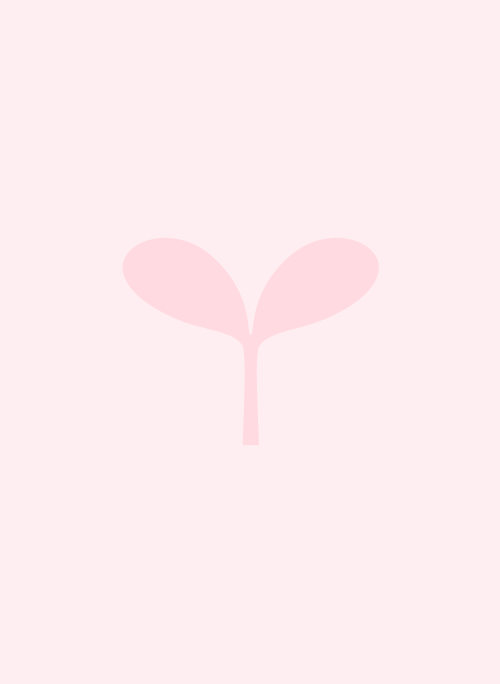同じ駅で降りた諒太と僕はT字路で左右に別れた。
「じゃあな」
「おう! ヒロ、女子高生に手を出すんじゃねえぞ」
「その言葉、風呂敷に包んでそのままお前に返してやるよ。諒太、女子中学生にちょっかい出すんじゃねえぞ」
「大丈夫だよ。俺は京香一筋だから」
「その言葉聞いて安心したよ。じゃな」
「おう」
左へ曲がった僕は十メートル程歩いて振り返った。二十メートル先には肩幅の広い背中がある。どんどん小さくなっていく背中を眺めながら、僕は口角を上げた。
僅か一ヶ月ぶりの帰省である。
「ただいまー」
玄関を開けると風呂上がりの妹がバスタオルも巻かずに出てきた。
「あ、お兄ちゃんお帰りー」
「お前なあ、もう二十一歳なんだぞ。いくら家族でも隠すところはちゃんと隠せ! 恥じらいという物を覚えろ」
※結菜の上にも下にもモザイクをかけてお読み下さいm(__)m
「はーい! ところでお兄ちゃん、彼女はできた?」
「その他に質問はないのか? ほら、ご飯ちゃんと食べてる? とか、お掃除はちゃんとしてる? とか」
「ない。元気そうだからそこには興味ないよ。で? 彼女はできた?」
「うるせー!」
「はあ、まだいないのか」
リビングに入ると僕の大好きな餃子がテーブルに並んでいた。
「母さん、ただいま」
「広海、お帰り。お腹空いたでしょ? 早く食べなさい。ところであんた、彼女はできたの?」
結菜は父さんの血が濃いはずである。けれど、話す内容は母さんと同じなのだ。なんとも面倒な母娘である。
面倒くさいので僕はつい口を割ってしまった。
「彼女みたいなのはいるよ」
「えー?」「えー!」「お兄ちゃん、快挙だね!」
普通、息子に彼女がてきたくらいでそんなに驚くか。しかも父さんまで。どれだけ僕がもてないと思ってんだよ。ったく!
明日から土日でゆっくりできる。けれど紗綾には時間がないのだ。僕は二人共助けたい。少しでも多くの人からの意見を聞く為、ますば妹に真実を話したのだ。四人、五人と寄ってくれば文殊の知恵はそれだけ増える事になる。
「そんな事があるの? 双子であるお兄ちゃんの話す事だから信用はしたいけど……」
寝る前、僕は妹を部屋に呼び相談にのってもらっている。
「したいけど……何? 僕が嘘ついてるとでも言いたいのか? ほら、これが証拠の日記だ」
僕は日記を開いて妹に見せた。
「どれどれ……。
六月二十日――晴れのち曇り。
昨日僕は、産まれて初めてキスをした。
二十一歳というかなり遅いファーストキスだった。
檸檬の味?
味など覚えていない」
しまった。最初のページを隠すのを忘れていた。
「ちょっ、ちょっと待った。次のページから読んでくれ」
「もう、読んじゃったもん。お兄ちゃん! ファーストキスも今年なの? ダサっ! 私たち、もう二十一歳なんだよ」
「うるさいなあ、そんな事ほっとけよ。次のページから読め!」
妹は次のページを開き読み始めた。
「左のページがお兄ちゃんの書いた文よね? で、この右のページが紗綾さんが書いたって事? 鉛筆やボールペンで書いたんじゃなくて、文字が浮き上がってるわね。こりゃ凄いわ」
「だろ? 二人共助けたいんだよ。なんかいい方法思い付いたら教えてくれよな」
「いい方法ねー。私頭悪いからなあ。あ、これって三年前の今日にしか行けないの? もしも五年前とか七年前にも行けるんだったらさ、京香さんに早期発見させれば移植受けなくても治せるんじゃない?」
妹なりに真剣に考えてくれているようだ。運動能力には秀《ひい》でているいるものの、小さな頃から勉強は全くできなかった。いつも僕が教えてやっていたのだ。けれど今僕たちが直面している問題は勉強ができるできないなど関係ないのかもしれない。
「五年前かあ。もしも行ければ問題は解決しそうだけど、三年前にしか行けないんだよね」
「そっかあ。それよりお兄ちゃん、お兄ちゃんの彼女ってどんな人? 同じ大学の人とか?」
嫌な質問をしてきたものだ。夢の中の紗綾が彼女だなんて言ったら妹はどんな反応をするのだろうか。紗綾とキスをし紗綾と結ばれた事など言えるはずもない。
「お前なんかよりぜんぜん可愛い女の子だよ。口うるさくもないし優しいし」
「すみませんね! 口うるさくて! ねえねえ、いいじゃん! 教えてよ。どんな人? 彼女の写真くらいあるんでしょ? ねえねえ、見せてよ。お兄ちゃん! ねえねえ」
ねえねえ、ねえねえと、本当に口うるさい妹である。そう言えば写真など撮った事がない。紗綾との写真。あまりにも不思議な出会いだった為、記念の写真を撮ろうだなんて思いもよらなかった。いや、女性経験が皆無な僕にはそこまで気が回らなかったのかもしれない。
今日はポケット付きのパジャマで眠る事にしよう。そのポケットにはスマホを忍ばせ紗綾と二人で自撮りをしよう。そしてその写真をスマホの待ち受け画面に設定するのだ。そう思うと僕はわくわくしてきた。
「ねえねえ、お兄ちゃん。何ニヤニヤしてんの? かなりキモいけど……」
妹にそう言われ僕は正気に戻った。
「ニヤニヤって何だよ」
「ケラケラでもワッハッハでもない、その笑い方の事よ。気持ち悪いから」
「うっせー! お前に相談したのが間違いだった。早く寝ろ。おやすみ」
僕の言葉に妹はすんなり部屋へと帰っていった。あまりにも素直すぎるので少し嫌な予感もしていたけれど、その嫌な予感は現実となった。
「よっこいしょっと」
「布団なんて持ってきて、お前何すんだよ」
妹はにやりと微笑んだ。
「何って、お兄ちゃんと一緒に寝るんだよ。その紗綾さんて子の事、助けたいんでしょ? 取り敢えず私も会っておかないと解決策も思い付かないでしょ? だから今日は一緒に寝てあげる」
「はあ? そこまで頼んでねえだろ! 部屋に帰れ。部屋に帰って体育館歩き続ける夢でも見てろ」
「そんな夢見たい訳ないでしょ! なんで夢の中でまで歩き続けなきゃなんないのよ。はいはい、もっと左に寄って下さいね。私の布団が敷けないでしょ!」
結局妹は無理やり僕の布団の隣に寝床を確保し眠りに就いた。