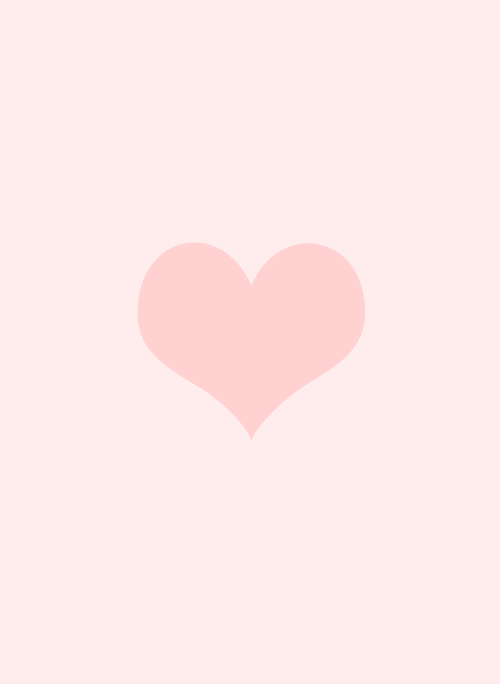現在の時刻は午後9時10分。今日の授業はもう終わっていてクラスメイトの人も誰一人として残っては居ない。
「試したいことがある。」
月宮君からこの言葉をここ最近毎日のように言われてきた私は、今こうして鏡の前に立っている。
うちの学校には各階の決められた廊下に大きな鏡がある。これといって何かに使われているわけでもないが。
「これでどうすれば良いの?」
早くここから立ち去りたい思いが私の口調を厳しくさせた。なぜなら私は、嫌いな自分がはっきり目に見えてしまう鏡が嫌いだからだ。
そんな冷たく放たれた言葉など聞こえていないのか
「左手を鏡にくっつけて、右手を自分の胸に当てて目を閉じて静かに息を吐いてみろ」
と彼は顔色一つ変えず指示を出す。
(今は、何を言っても無駄か。)そう思った私は、彼の指示通りに行動を起こした。
静かに息を吐きはじめると辺りが明るくなるのがわかった。まるでステージのスポットライトを浴びているかのような明るさ。目を閉じていてもしっかりと光は届いているあの感覚。
・・向かないよ、あの子には・・
いきなり走馬灯が頭を駆け巡る。
・・大丈夫、私がついてるよ!・・
「「やめて」」
・・私は味方だからね!・・
「「聞きたくない」」
・・何があっても守ってあげる!・・
「「いや」」
「おい!カンナ!?」
「「お願い、もう」」
「しっかりしろ!!」
「「私に関わらないで!!!!」」
・
・
・
どれだけの時間が流れたか今の私には分からない。
あの時何が起こったのかさえ分からないから。
「あ、目が覚めたみたいだな。」
部屋に入ってきた月宮君が声をかけてきた。
ゆっくり体を起こし辺りを見渡してみる。そこはいつも見慣れた自分の部屋だった。
「具合は、どうだ?いきなり倒れるから心配したぞ?」
月宮君が、少し困ったような それでいて優しい笑みをこちらに向ける。始めて会った時とはまた別の笑顔だった。いつも無表情しか見ていない為か少し新鮮に思えた。
「ごめんなさい。何でもないの・・・。」
これ以上迷惑はかけられない。話したところで何かが変わるわけでもないから。
「そっか・・・。」
月宮君は何か言いたげな表情を一瞬見せたが、またいつもの無表情に戻す。
「あの・・・私たちって学校に居たんじゃなかったっけ?」
学校までの記憶しかない私は、自分がなぜ自分の家のベッドで横になっているのかがわからなかった。いつの間に帰ってきたのだろうか・・・。
「俺がここまで連れてきた。」
あたかも当然だと言わんばかりに力強く放たれた言葉に、私は妙な違和感を抱いた。
(ん?どうやって?)最初の疑問だった。
第一彼は私以外の人には見えず、物には触れることが出来ても人には触れることが出来ないのだ。実際、教室で空いている席に座っているところを見たことがあるし授業をしている先生の肩に手を置こうとして通り抜けているのをこの目で確認済みだからだ。
「人に触れるようにしたんだよ。お前を抱えて空飛んできた。以上。」
彼の放つ言葉はどうして私の理解を超えるようなことばかりなのだろうか。
壁時計では丁度11時を指していた。
「試したいことがある。」
月宮君からこの言葉をここ最近毎日のように言われてきた私は、今こうして鏡の前に立っている。
うちの学校には各階の決められた廊下に大きな鏡がある。これといって何かに使われているわけでもないが。
「これでどうすれば良いの?」
早くここから立ち去りたい思いが私の口調を厳しくさせた。なぜなら私は、嫌いな自分がはっきり目に見えてしまう鏡が嫌いだからだ。
そんな冷たく放たれた言葉など聞こえていないのか
「左手を鏡にくっつけて、右手を自分の胸に当てて目を閉じて静かに息を吐いてみろ」
と彼は顔色一つ変えず指示を出す。
(今は、何を言っても無駄か。)そう思った私は、彼の指示通りに行動を起こした。
静かに息を吐きはじめると辺りが明るくなるのがわかった。まるでステージのスポットライトを浴びているかのような明るさ。目を閉じていてもしっかりと光は届いているあの感覚。
・・向かないよ、あの子には・・
いきなり走馬灯が頭を駆け巡る。
・・大丈夫、私がついてるよ!・・
「「やめて」」
・・私は味方だからね!・・
「「聞きたくない」」
・・何があっても守ってあげる!・・
「「いや」」
「おい!カンナ!?」
「「お願い、もう」」
「しっかりしろ!!」
「「私に関わらないで!!!!」」
・
・
・
どれだけの時間が流れたか今の私には分からない。
あの時何が起こったのかさえ分からないから。
「あ、目が覚めたみたいだな。」
部屋に入ってきた月宮君が声をかけてきた。
ゆっくり体を起こし辺りを見渡してみる。そこはいつも見慣れた自分の部屋だった。
「具合は、どうだ?いきなり倒れるから心配したぞ?」
月宮君が、少し困ったような それでいて優しい笑みをこちらに向ける。始めて会った時とはまた別の笑顔だった。いつも無表情しか見ていない為か少し新鮮に思えた。
「ごめんなさい。何でもないの・・・。」
これ以上迷惑はかけられない。話したところで何かが変わるわけでもないから。
「そっか・・・。」
月宮君は何か言いたげな表情を一瞬見せたが、またいつもの無表情に戻す。
「あの・・・私たちって学校に居たんじゃなかったっけ?」
学校までの記憶しかない私は、自分がなぜ自分の家のベッドで横になっているのかがわからなかった。いつの間に帰ってきたのだろうか・・・。
「俺がここまで連れてきた。」
あたかも当然だと言わんばかりに力強く放たれた言葉に、私は妙な違和感を抱いた。
(ん?どうやって?)最初の疑問だった。
第一彼は私以外の人には見えず、物には触れることが出来ても人には触れることが出来ないのだ。実際、教室で空いている席に座っているところを見たことがあるし授業をしている先生の肩に手を置こうとして通り抜けているのをこの目で確認済みだからだ。
「人に触れるようにしたんだよ。お前を抱えて空飛んできた。以上。」
彼の放つ言葉はどうして私の理解を超えるようなことばかりなのだろうか。
壁時計では丁度11時を指していた。