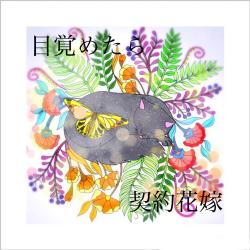冬馬が手に持っていた紙を俺に渡し、部屋を出ていこうとしている。
「冬馬、ありがとう。」
「自分自信を苦しめる罠は仕掛けるなよ。」
「まったくだ。」
冬馬の背中を見送り、見えなくなると目を閉じて花菜を思い浮かべる。
あの日、彼氏にフラれた花菜は俺の進める甘いカクテルを次々と飲んでいた。
窓から見える夜景も手伝い、ご機嫌でカクテルを飲み進めていたが、酔いが廻ると愚痴を溢し始めていた。
『なんか眠い………。』
花菜の一言に罠を仕掛けた。記憶が曖昧な花菜を嵌めるのは簡単だったが―――。
「見張る必要があるな。」
知らない男の中で飲ませられるか。
あの日の花菜の酔い潰れた姿が脳裏を横切る。
「チッ……、何が飲み会だ。」
花菜と泊まる宿に目星をつけて予約ボタンを押した。
「待ってろよ、花菜。温泉でも楽しむぞ。」
静かな社長室に俺の低い声だけが響いた。
「冬馬、ありがとう。」
「自分自信を苦しめる罠は仕掛けるなよ。」
「まったくだ。」
冬馬の背中を見送り、見えなくなると目を閉じて花菜を思い浮かべる。
あの日、彼氏にフラれた花菜は俺の進める甘いカクテルを次々と飲んでいた。
窓から見える夜景も手伝い、ご機嫌でカクテルを飲み進めていたが、酔いが廻ると愚痴を溢し始めていた。
『なんか眠い………。』
花菜の一言に罠を仕掛けた。記憶が曖昧な花菜を嵌めるのは簡単だったが―――。
「見張る必要があるな。」
知らない男の中で飲ませられるか。
あの日の花菜の酔い潰れた姿が脳裏を横切る。
「チッ……、何が飲み会だ。」
花菜と泊まる宿に目星をつけて予約ボタンを押した。
「待ってろよ、花菜。温泉でも楽しむぞ。」
静かな社長室に俺の低い声だけが響いた。