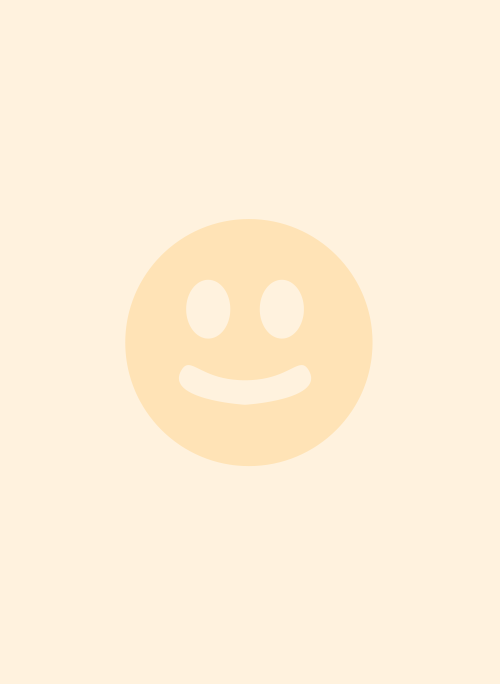「・・・肩書きが好きな子だって確かにいるだろうけど、そんな子ばかりじゃないし、弘平はまだモテるでしょう?どうしてそんなにシュンとしてるの?俺は格好いいって自分で言ってたじゃない」
彼は苦笑した。
「うん、だから、外見ね。会社辞めて、でも実家が金を持ってるって判ったらまた連絡がくるようになった子もいた。ハッキリ言われたよ、『外見が良くても無職じゃどうしようもないって思ったけど、実家がお金持ちなんだってね?だったら何も問題ないよね!』だってさ。それを本人に言うところが凄くない?」
・・・それは凄いよね。呆れて、私は頷いた。何て露骨な人なんだ・・・メンタルも強そうな女性だ。
「さすがに腹が立った。祖父や親父の力で大きくなった会社は、俺には関係ない。兄弟も多いし、跡だって継がない。投資がそこそこ上手くいってるから確かに金銭的には困ってないけど、それって俺じゃなくてもいいってことだよな?って。外見なんていつかは崩れるし、金に困ることになったら捨てられるわけ?って。だけど――――――」
弘平が窓枠から肘をおろして、体を私へ向ける。
「俺だって、そういう面を利用してたんだよなって思った。それで、お前に―――――ナギに、凄く失礼なことしたんだって。お前が俺を褒めてくれるのは、いつも内面の良いところだったのに。性格とか、行動とかだったのに。だから謝らなきゃってずっと思ってたんだ。―――――――ごめんな。別れたときのこと、酷かったと思ってる」
びっくりした。
私は驚きのあまり、タクシーの座席でカチンコチンに固まってしまったようだった。