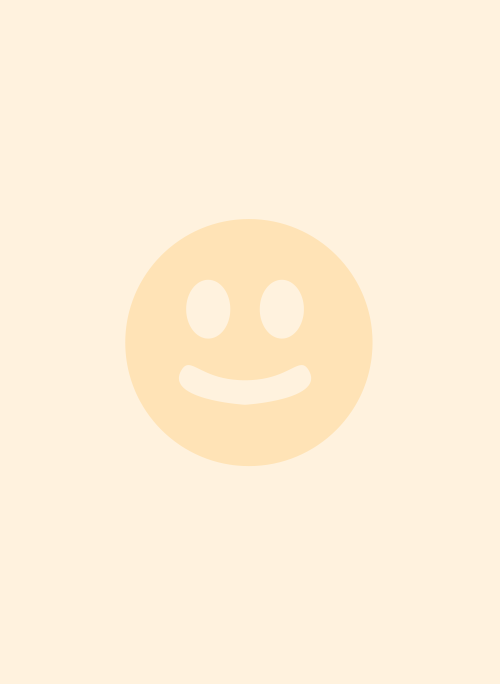「・・・と、とにかく、ジャムル君と仲が良さそうでそれは良かったわ。・・・ええと、で、よ。で!」
「で?」
ようやく寝たらしい赤ちゃんの香織ちゃんを、伊織君を追い立てたあとで綾はそっとソファーに寝かせる。その表情はまさしく「母親」だった。
「・・・どうして私の貯金持って逃げたの?」
綾がしゃがみ込んだ床の上から私を見上げた。穏やかな顔で。
「ジャムル君と何があってそういうことにしたの?どうして相談してくれなかったの?一体―――――――」
「彼のお母さんがね、危篤になったの」
綾の静かな声が部屋に響いて、私は言葉を途中でなくしてしまった。
「ジャムルの兄弟から電話が来てね、母親はもうもちそうにないって。そもそも母親の治療費のために日本に稼ぎに来ていたから、彼はどうしても帰るって言ってきかなかった。その電話がきてすぐに一緒に行こうって決めたの」
「・・・ジャムル君の、お母さん?」
「病気だったんだって、ずっとね。彼はよく話してた。それで電話がきて、すぐにインドに戻るっていって、でも収入は全部家族に仕送りしていてお金がないってなって・・・。相談する時間がなかったんだよ。あの時、凪は久しぶりの飲み会があって、夜帰ってくるのがいつもより遅かったでしょう」
・・・そう、だっけ?私は既に薄れて消えつつあった記憶を探った。
綾が失踪した日の前日。私は―――――――・・・ああ、確かにそうだった。終電で帰ってきて、だから、その日は朝、会社に行く前に綾と話しただけだったのだ。