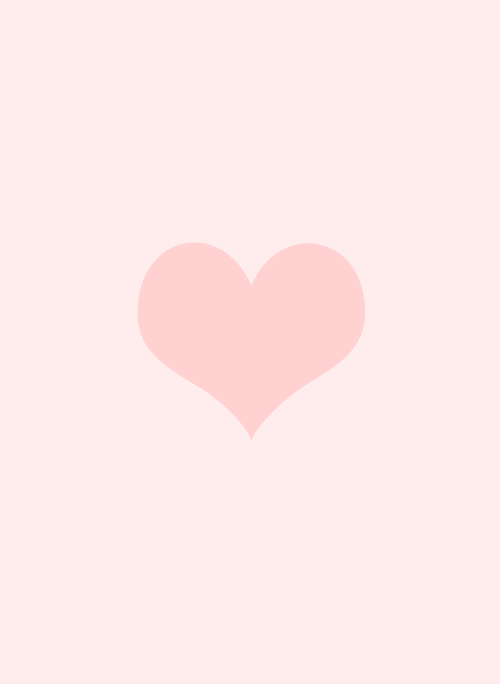「そんな無防備でいるとまた襲われちゃうよ?
いつも俺が、そばに居るわけじゃないんだしさ」
なにそれ、なんかズルいよ。
熱い。
全身が熱に侵される。
苦しい。
息ができない。
……甘い。
耳が溶けそう。
耳元から顔が離れていき、亮ちゃんの目が私の顔を見つめる。
……もう、やだ。
今の私の顔みないで。
「……もう、分かったから離して」
口に出して懇願する。
「分かってくれた?」
亮ちゃんは私が本当に分かったのか確認するように言った。
「分かったてば!」
私の主張にやっと納得し、やっと手の拘束が解けた。
キッっと目の前の相手を一瞥し、
「もう、亮ちゃんのばか!寝る!」
と言い、私はスタスタと寝室へと向かった。
熱い、熱い、熱い。
離れてもいつまでも熱が収まらない。
私をこんなふうにしてしまう亮ちゃんなんて、
「……きらい」
ぼそっと呟いた。
そして、そんなことをぐるぐると考えている私には、
「まぁ、どこにいても、どんな状況でも守ってみせるけどね」
という亮ちゃんの声は届かなかった。