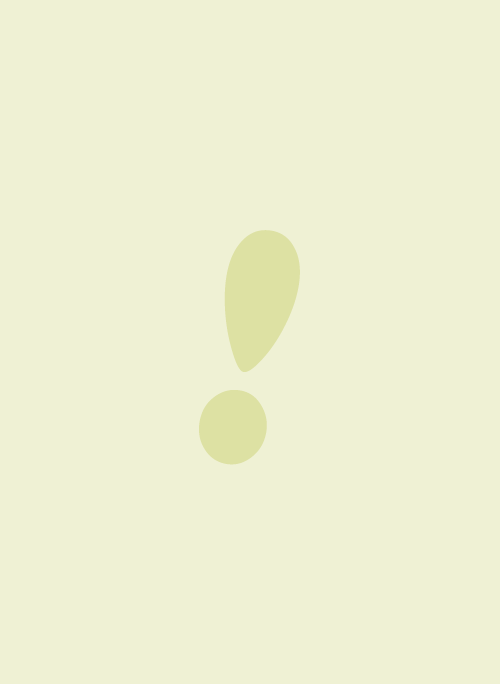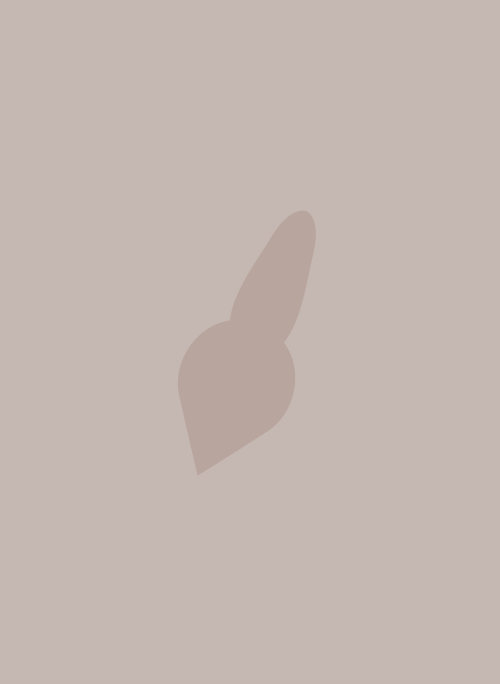「どうだった?この版は」
「最高」
「やりすぎじゃない?私もあんたみたいになっちゃうの?」
満面の笑みで、楽しかったよ、と答えた。
「でももう飲みたくないね。なんで一番嫌な記憶を呼び起こすの?」
「そうした方がいいっていうのを、あなたが身をもって証明したじゃない」
「そうだね。これでもう、あいつらにからかわれないでしょう」
「むしろ、学校に来られるのかなあ。あ、でもその時はまたこれがあるか。」
「あんたも飲む気?」
「もちろん。手に入れた本人が、実際試すほかないでしょう?」
そう言って彼女も赤い薬を飲んだ。
しばらく悶(もだ)えた後、目の色を変えて走っていった。
「はあ、疲れたなあ」
そう呟いて、私は眠った。
ある日の放課後。1人の少女と、1本の小瓶のお話。
ー了ー