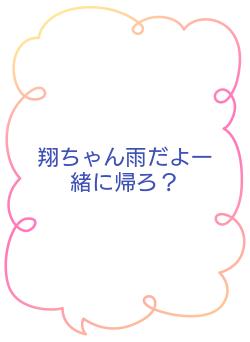年明け最初に見る顔が麻里の寝起きの顔ってのも悪くない。ていうかそれって、かなりしあわせかも。
完全な眠りに堕ちたのか背中の麻里が急に重くなった。その重力をしっかり受け止めながら、俺は夜空を見上げた。
さっきまで明るい光を放っていた月は、もう半分ほど雲のうしろに身を隠していた。その最後の光に俺はあわてて願いをかけた。
『もし彼女が都会で道に迷ったら、その柔らかな光で彼女の足元を照らしてください。憧れだったこの靴に慣れなくて靴擦れとかできちゃったら、いちばんに俺のところに帰ってこれるように。』
おぼろげな光が雲のうしろに消えて、俺が吐いた白い息がはっきり見えた。すこし悩んでさっきの願いを取り下げることにした。間に合わないかもしれないけど……。
『やっぱ今のなし! 麻里の眠りがなにものにも邪魔されませんように。』
彼女のちいさな寝息を耳元に感じながらそんなことを思って、満たされた気持ちで俺は夜空のしたをゆっくりと歩いた。
おわり。
完全な眠りに堕ちたのか背中の麻里が急に重くなった。その重力をしっかり受け止めながら、俺は夜空を見上げた。
さっきまで明るい光を放っていた月は、もう半分ほど雲のうしろに身を隠していた。その最後の光に俺はあわてて願いをかけた。
『もし彼女が都会で道に迷ったら、その柔らかな光で彼女の足元を照らしてください。憧れだったこの靴に慣れなくて靴擦れとかできちゃったら、いちばんに俺のところに帰ってこれるように。』
おぼろげな光が雲のうしろに消えて、俺が吐いた白い息がはっきり見えた。すこし悩んでさっきの願いを取り下げることにした。間に合わないかもしれないけど……。
『やっぱ今のなし! 麻里の眠りがなにものにも邪魔されませんように。』
彼女のちいさな寝息を耳元に感じながらそんなことを思って、満たされた気持ちで俺は夜空のしたをゆっくりと歩いた。
おわり。