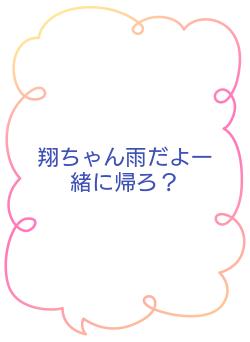「そんなに痛かった?」
「いや、たいしたことないよ」
まっすぐ、不安げに見上げるからいとおしくってキスをした。
「はい、おしまい。いくよ」
手を引いて夜の公園を歩き出す。
「えー」
不服そうな顔も可愛い。
可愛いけどすでに足の裏は真っ黒なはず。見た目が大人っぽくなっても、中身はちっとも変わってない。
「おい、ヒール片っぽどこいった?」
「あー。たぶんアレだ」
麻里が宙を指差した。
見上げるとサクラの樹の入り組んだ枝に、ベージュのヒールが突き刺さっていた。
(JIMMY CHOO )
この綴り知ってる。麻里が高校の頃から憧れてたちょっとお高いブランドだ。ファッション誌をめくりながらうっとりしてたっけ。
木の向こう側にぽっかり浮かぶ月が、小枝の隙間から柔らかな光をこぼしている。その光がヒールの甲をそっと照らす。夜の目印みたいだ。
「ほら」
半ば強引に麻里をおぶって、靴を取らせた。
「降りないの?」
「……もうちょっとだけ」
「別にいいけど……」
俺の背中にぴったり顔をくっつけている。
「いや、たいしたことないよ」
まっすぐ、不安げに見上げるからいとおしくってキスをした。
「はい、おしまい。いくよ」
手を引いて夜の公園を歩き出す。
「えー」
不服そうな顔も可愛い。
可愛いけどすでに足の裏は真っ黒なはず。見た目が大人っぽくなっても、中身はちっとも変わってない。
「おい、ヒール片っぽどこいった?」
「あー。たぶんアレだ」
麻里が宙を指差した。
見上げるとサクラの樹の入り組んだ枝に、ベージュのヒールが突き刺さっていた。
(JIMMY CHOO )
この綴り知ってる。麻里が高校の頃から憧れてたちょっとお高いブランドだ。ファッション誌をめくりながらうっとりしてたっけ。
木の向こう側にぽっかり浮かぶ月が、小枝の隙間から柔らかな光をこぼしている。その光がヒールの甲をそっと照らす。夜の目印みたいだ。
「ほら」
半ば強引に麻里をおぶって、靴を取らせた。
「降りないの?」
「……もうちょっとだけ」
「別にいいけど……」
俺の背中にぴったり顔をくっつけている。