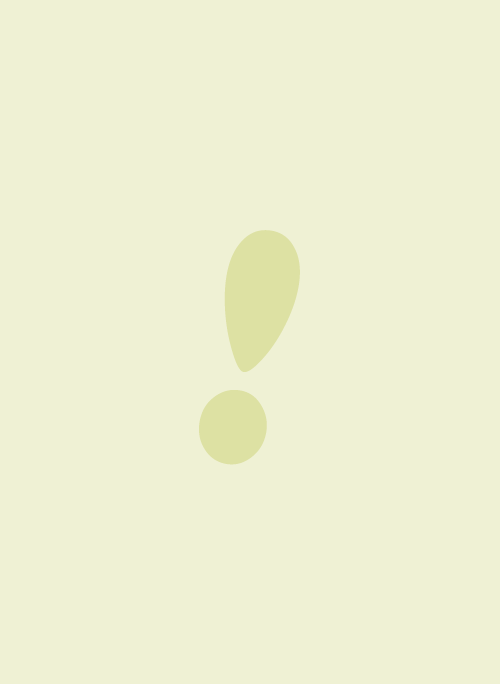「……そ、そんなこと……あたしにとって……圭祐君は……」
首を横に振ってなにか言いかけた央子の目からは見る見るうちに涙が溢れてきて、とうとう堪えきれずにわあっと泣き出してしまった。
俺は、慌ててポケットを探って入れた覚えのないハンカチを探してみたが、やっぱりそんな気の利いたものは出てこない。
結局俺は、央子の頭を抱えて俺の胸に抱き寄せた。
しばらくの間俺の胸に顔を埋めて声を殺して泣き続ける央子。
俺には、俺の腕の中で泣いている央子が、普段よりも一回りも二回りも小さくなったように思えた。
「ごめんな、気付いてやれなくて」
央子の長い髪を何度も撫でながらそう繰り返す。
ただ、首を横に振って泣き続ける央子。
今まで胸の内に溜めていたものを全て吐き出すかのように、央子はずっと泣き続けた。