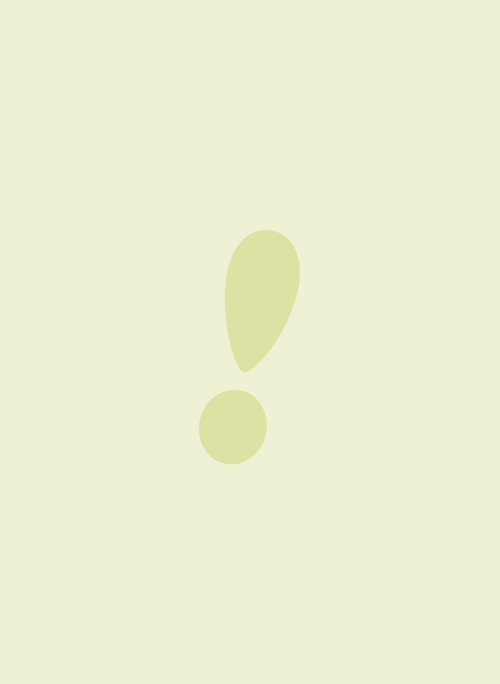その悠聖のひたむきな姿は、彼がどんなに咲雪のことを深く想ってくれていたのかまざまざと見せ付けるものだった。
ほんとにごめん。
そんな悠聖の姿を見ていると、悠聖をだましていたことを申し訳なく思う気持ちでいっぱいになってしまった。
「圭祐君、大丈夫?立てる?」
央子がまだ地面にひざをついたままの俺に、自分のみぞおちの辺りを指差しながら尋ねてくる。
「まあ、こっちは何とか痛みも引いてきたけど、今の悠聖の言葉がさ、ちょうど胸のこの辺にグサグサッてきてさ……なんか、殴られた痛みよりこっちの方がダメージが大きいんだよね。
……まあ、これは自業自得なんだけど。でも、特に悠聖のあんな姿を見せられると、もっと早く教えてれば誰も傷つかずに済んだのにな……ってさ」
俺がそう答えると、央子はゆっくりと首を横に振った。